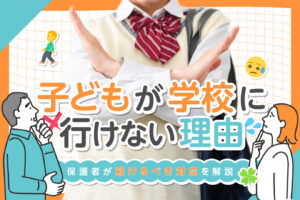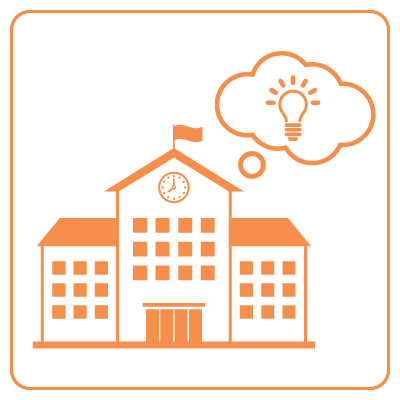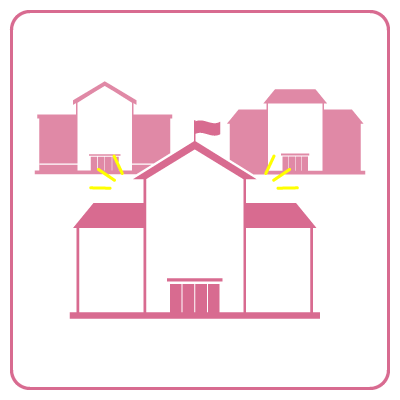不登校中のお子さんが家でゲームばかりしていると、保護者の方は「ゲーム依存になるのでは」と心配になるでしょう。ゲームのやりすぎを防ぐために禁止しようとすると、かえって逆効果になる場合もあるため注意が必要です。
今回は、ゲーム依存の影響と不登校中にゲーム依存になる理由、防ぐ方法を解説します。お子さんのゲーム時間が気になる方は、参考にしてみてください。
不登校中の子どもが心配!ゲーム依存の影響
ゲーム依存とは、ゲームのやりすぎによって、その行為が引き起こす問題が悪化することを指します。
ゲーム依存になると、心身にさまざまな悪影響を及ぼすことがわかっています。ここでは、大きな2つの影響を紹介します。
生活リズムが乱れる
ゲーム依存によって睡眠不足になると、生活リズムが乱れます。その結果、身体に次のような影響が及ぼされます。
●摂食障害
●視力の低下
●眼精疲労
●頭痛
●筋痛
ゲームのやりすぎが原因で、上記のような症状が見られる場合は、医療機関への相談が必要です。
気力が低下する
生活リズムの乱れやそれによる身体の不調が続けば、気力の低下が引き起こされます。場合によっては、うつや不安症などの精神症状も合併することがあるのです。
ゲーム以外には何もしたくないという状態になっていれば、ゲーム依存が疑われます。重症化すると、ゲームにすら興味を示さなくなる無気力状態になる可能性もあるため、早めに医療機関へ相談する必要があります。
不登校の理由=ゲーム依存ではない可能性に注意
不登校の理由がゲーム依存の場合もあるが、そうではないこともあります。もし、不登校になる前からお子さんがゲームに熱中していた場合は、ゲームが悪いと決めつけず、不登校の理由や原因を探ることが大切です。
ゲーム以外が理由で不登校になっているときは、ゲームがストレス発散や居場所になっており、本人の支えになっている可能性があります。そのため、すぐに禁止したり取り上げたりせず、子どもの気持ちに寄り添うことが必要です。
関連記事:不登校になる心理とは?子どもの心理や長期化しないための方法を紹介|通信高校生ブログ|明聖高等学校
不登校中の子どもがゲーム依存になる理由
不登校中の子どもがゲーム依存になる理由は、さまざまあります。ここでは、4つの理由を解説するので、お子さんに当てはまるものがないか確認してみてください。
ゲームが現実逃避の手段になっている
不登校中のお子さんは、さまざまな葛藤を抱えています。将来に不安を感じ「学校復帰しなければならない」と焦る一方、不登校のきっかけとなった人間関係や学業不振の悩みが解消せず、「何かしなければいけないけれど、どうすればいいかわからない」と感じている状態です。
このような心理状態で、ほかに夢中になれるものがないと、ストレスや不安を解消するために、ゲームに熱中してしまうことがあります。
不登校中は日中の外出が難しいため、手っ取り早く現実を忘れられるゲームに手を伸ばしてしまいがちになるのです。
ゲームが居場所になっている
プレイヤー同士が交流できるオンラインゲームをしている場合は、そのコミュニティが子どもの居場所になっていることもあります。
学校などリアルな世界での人間関係に悩む子どもにとって、共通の趣味で結ばれたゲーム内の仲間は、唯一のよりどころになりやすいのです。相手の顔が見えないからこそ、「気軽に関われる」「社交的になれる」などのメリットもあります。
「仲間に認められたい」という想いがエスカレートすると、ゲーム内のランクを高めようと、際限なく課金してしまう場合もあるため、注意が必要です。
関連記事:居場所がない原因とは?対処法と新たな選択肢を解説|通信高校生ブログ|明聖高等学校
ゲームで友達とつながっている
ゲームを通じて学校の友達とつながっていると、「友達と遊ぶ手段がゲームしかない」「誘われたら断れない」といった状況になることがあります。
友人関係を維持するためにゲームをやらざるを得なくなる子もいるのです。
依存しやすいゲームが増えている
近年主流となっているオンラインゲームは、オフラインゲームよりも依存性が高いといわれています。依存性が高いのは、次のような特徴があるためです。
●無料ではじめられるにもかかわらず、アップデートが繰り返されて終わりがない
●ガチャ課金システムのようにギャンブル性が強い
●ログインボーナスやイベント開催などが頻繁にあり、プレイしないと手に入らないアイテムがある
●ランクや成績が可視化されることで、他者との競争意識が強化される
●ゲーム内で仲間とつながることで非日常感を味わえる
これらの要素は、子どもも大人も関係なく、ゲームに熱中させやすくします。
不登校中のゲームの禁止は効果ある?
不登校中の子どもがゲームをやりすぎているときは、ゲームの禁止が効果的に働くこともあります。ゲームの禁止は、ゲーム依存からの回復方法としても有効とされており、最終的なゴールに設定されることもあるのです。
ただし、ゲームの禁止を強制すると、暴力や暴言、非行など別の問題が発生することもあるため注意が必要です。
ゲームの禁止によって不登校が改善されるとは限らず、子どもによっては、ゲームの禁止はゴールにならないこともあるでしょう。せっかくのコミュニケーションの機会やストレス発散法を奪うことになり、心身の状態がさらに不安定になることもあります。
そのため、ゲームを一切禁止するよりも、ゲーム時間を減らしたり別の方法に置き換えたりなどの方法で対応するのが現実的です。
不登校中の子どもがゲーム依存になるのを防ぐ保護者の対応
不登校中の子どもに対して、ゲームを禁止する以外に有効なゲーム依存を防ぐ方法を紹介します。
適切な声かけと見守りを意識する
ゲーム依存を防ぐためには、ゲームのやりすぎを放置しないことが重要です。そのためには、適切な声かけと見守りが求められます。
保護者の方は、お子さんが納得できるルールを設定するために、本人がプレイしているゲームのタイトルや種類、友達を把握しておきましょう。
ゲームの内容がわかれば、時間で区切る以外にも、一段落させる方法がわかります。例えば、区切りをつけにくいゲームは「次のステージまで行けば一旦休憩する」といった方法です。
お子さんと話し合ったうえで、明確にルールを決めたあとは、お子さんにとって心地よいと感じられるフレーズを使った声かけをおこないます。「時間だからゲームをやめて」よりも「あと5分で終わりだからそろそろ区切りをつけてね」などのほうが、お子さんも受け入れやすいはずです。
もし、お子さんがルールを守れなかったときは、落ち着いて保護者の考えや気持ちを伝えましょう。「あなたが約束を守れなくてかなしい」「あなたはどう思っているの?」などです。
関連記事:不登校の子どもに適切な対応をするために。家庭での向き合い方と利用できる施設を解説|通信高校生ブログ|明聖高等学校
長時間ゲームができない仕組みを作る
お子さんがゲーム依存になる前に、ゲームを長時間できない仕組みを作っておくのも有効です。例えば、以下の方法があります。
| ゲームを長時間できない仕組み | 具体例 |
|---|---|
| ネット機器やゲームは保護者が貸し出す | ・ルーターは保護者が管理し、決めた時間になったら切断する ・ゲーム機器は保護者からのレンタルにし、ルールを守れない場合は貸し出さないようにする |
| 時間と場所を決める | ・保護者の目が届くリビングで、保護者が家にいる18時から20時までゲームを許可する ・寝るときは保護者にゲーム機器やスマートフォンなどをすべて預ける |
| お金の使い方を決める | 毎月1,000円は自由に課金してよいが、追加で課金したい場合は保護者に相談させる |
| 設定を管理する | ゲームを起動できる時間を2時間に設定する |
上記のいずれか、または組み合わせてゲームを長時間できない仕組みを作ります。ゲームをできない時間で子どもが熱中できることを探しておくことも大切です。そして、ゲームをしていないことをほめるようにし、肯定的なコミュニケーションをとりましょう。
本人も保護者も納得できるルールを作る
ゲームのプレイ時間や頻度をコントロールできるよう、ルールを設定してみましょう。保護者が一方的にルールを押しつけるのではなく、話し合いながら双方が納得できるルールを設けることが大切です。
ルールを設定したあとは、子ども自身がルールを守れるかどうかを見守ります。数日間様子を見て、本人だけではなかなかルールを守れないのであれば、保護者からも声をかけましょう。
あらかじめ、ルールを守れなかったときにどうするかを決めておく方法もあります。理由と期間、返却の条件を決めてから一時的にゲームを預かるのも有効です。
一度ルールを決めても、繰り返し話し合って柔軟に変更していくことも大切です。また、家族全員が同じルールを守ってゲームを楽しむことで、ルールの定着を図れます。
不安やストレスを解消できるほかの活動を習慣づける
ゲーム以外に不安を紛らわしたり、ストレスを発散したりできるほかの方法を見つけることも大切です。
読書、イラスト、工作、スポーツ、音楽など、本人が興味を持ったことに打ち込めるよう、保護者はサポートしましょう。
また、がんばりを保護者が積極的に褒めて、認めてあげれば、子どもにとって新たな心のよりどころを作れるはずです。
ただし、依存対象がゲームからほかのものに移っただけでは、あまり状況が改善したとはいえません。例えば、イラストに熱中しながら、ゲームも楽しみ、心の余裕があるときには勉強や家事もして、と、さまざまな活動ができるようになるのが理想的です。
時間や金銭的な価値を理解させる
ゲームで消費している時間やお金の正しい価値と、それを別のことにも充てる重要性を理解させることも大切です。
子どもたちはゲームの時間を有意義なものととらえていますが、長い人生のなかで総合的に見たとき、そうとは限りません。
限られた子ども時代をゲームだけに費やすことのデメリットに触れつつ、ほかのことにも目を向けさせましょう。
不登校中の子どもがゲーム依存で手に負えなくなったとき
どうしてもルールを守れない、子どもが暴力をふるうなど、症状の悪化が見られたら専門機関に相談することが大切です。
ゲーム依存に対する専門機関は全国各地にあります。近くの専門機関を調べて、まずは保護者の方だけでも相談に行ってみましょう。
まとめ
不登校中、不安や悩みを抱えた状態でゲームに依存してしまうと、社会生活に支障をきたす心の病につながることもあります。
親子で問題に向き合い、子どもが自ら変わっていこうとするのを、保護者は後押ししていきましょう。少しでも困難があれば、カウンセラーや医療機関の助けも借りてみてください。
参考URL:
ゲーム依存相談対応マニュアル|久里浜医療センター
ネット依存による健康被害|総務省
オンラインゲームをやめさせてほしい|特定非営利活動法人 教育研究所
ゲーム依存、どうしたら?悩む当事者や家族 識者「『取り上げたら済む』は短絡的」|西日本新聞
不登校になる心理とは?子どもの心理や長期化しないための方法を紹介|通信高校生ブログ|明聖高等学校
居場所がない原因とは?対処法と新たな選択肢を解説|通信高校生ブログ|明聖高等学校
不登校の子どもに適切な対応をするために。家庭での向き合い方と利用できる施設を解説|通信高校生ブログ|明聖高等学校

明聖高等学校は、千葉・中野にキャンパスを構える通信制高校です。全日コース・全日ITコース・通信コース・WEBコースに分かれており、一人ひとりに合わせた高校生活を過ごすことができます。