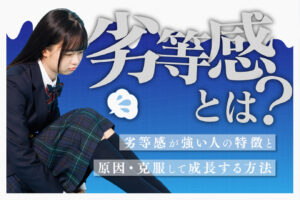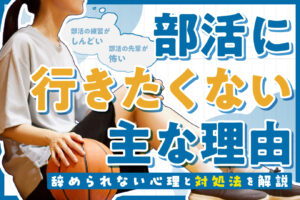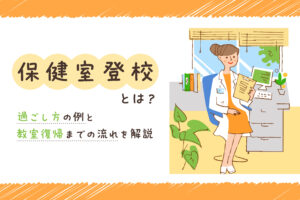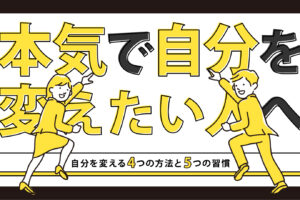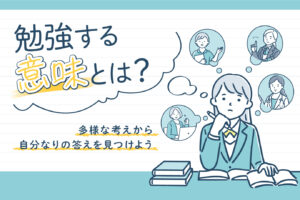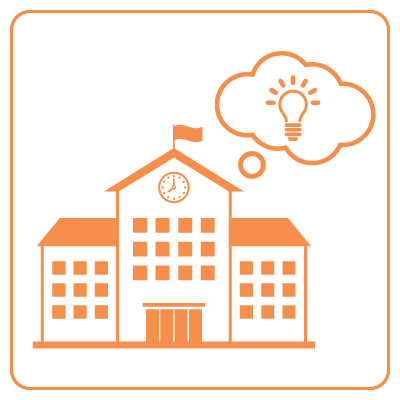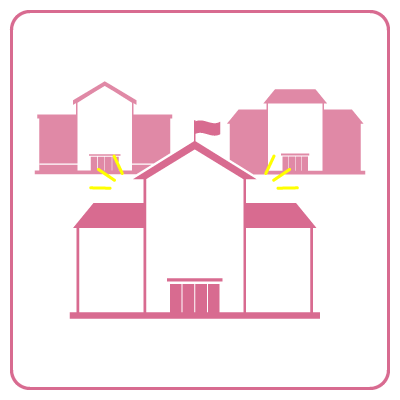「今日は学校、休みたいな…」そんな日もありますよね。理由はうまく説明できないけれど、疲れがたまっていたり、朝起きたときに体がだるかったり、学校のことを考えると気が重くなってしまったり…。誰にでも「休みたい」と感じる日はあるものです。
この記事では、学校を休みたいと感じたときに使える理由の例や、どう伝えればいいかについて紹介しています。無理せず、あなたの心と体を大切にするための参考になれば幸いです。
ただし、元気に登校できる状態であれば、なんとなくの気分でサボることはおすすめしません。学校を休むのは、心や体がしんどいときです。
1日だけ学校を休む理由・言い訳の例文
まずは、1日だけ学校を休みたいときに使える理由や言い訳を例文つきで紹介します。
関連記事:「学校に行きたくない」ときは無理しないで。休みながら自分に向き合う|通信高校生ブログ|明聖高等学校
体調不良
寝不足でだるい、頭が痛い、気分が悪いなど。そんな日は、無理をせず1日だけ休むのもひとつの選択です。体がしんどいときは、しっかり休むことも大切です。
ただし、仮病を使って休むことはおすすめできません。「なんとなく行きたくないから」といった理由でサボるのではなく、本当に体調が悪いときに限って使うようにしましょう。
●朝から頭痛と熱の症状があるため、本日はお休みさせていただきます
●体調がすぐれず、無理をさせないよう今日は欠席させていただきます
●昨夜から腹痛が続いているため、念のためお休みさせていただきます
●風邪のような症状が出ており、感染予防のため欠席します
学校を休むとき、体調不良はもっとも保護者が納得しやすい理由でもあります。具体的な症状とあわせて、1日だけ学校を休みたい旨を伝えましょう。
家の用事
家の事情で学校を休まなければならないこともあります。この場合、理由を詳しく話さなくても、先生に過度に心配されることは少ないため伝えやすい理由のひとつです。
ただし、あくまでも本当に家の用事があるときに限って使うようにしましょう。サボるために作り話をすると、後からトラブルになることがありますし、信用を失ってしまうこともあります。
また、保護者に黙って勝手に理由を作るのはNGです。きちんと相談して、「家の用事ということで学校に伝えていいか」を確認しておきましょう。
●家庭の事情により、本日は欠席させていただきます
●急きょ外出の予定が入り、本日はお休みをいただきます
●家族の付き添いが必要となり、本日は欠席させていただきます
●法事に出席するため、本日は学校をお休みいたします
「家の用事」は便利な理由ですが、あくまで正当な事情があるときに使うようにしましょう。1日休んで気持ちをリセットしたいときは、保護者としっかり話し合って判断することが大切です。
学校に関する悩み
人間関係や勉強、学校の雰囲気などで気持ちが沈んでしまうときは、無理をせず1日だけ休んで心と体を整えることも大切です。「学校に行くのがつらい」と感じる日は、しっかりと休んで、エネルギーを回復させましょう。
ただし、これは気分的なサボりとは違います。本当にしんどいときにこそ、自分を守る手段として使ってください。
●精神的に不安定な状態のため、本日はお休みさせていただきます
●心身の調子が整わず、登校が難しいため欠席いたします
●現在、学校生活に関することで悩みがあり、本日は静養のため欠席させていただきます
●登校に不安を感じており、本日は様子を見ながら休ませていただきます
信頼できる先生がいる場合は、悩みを伝えて相談するのも良い方法です。ただし、「あまり深く関わってほしくない」「話すのが負担」という場合は、無理をして伝える必要はありません。
なんとなく
とくにハッキリとした理由はないけれど、「今日は学校に行きたくない」と感じる日もあるかもしれません。そんなとき、無理に行こうとして心や体に負担がかかってしまうくらいなら、1日だけ休んで整えるという選択肢もあります。
ただし、「サボりたいからなんとなく休む」のとは違います。しんどさを感じているときに、自分を守るための休みとして使いましょう。
●体調に大きな問題はありませんが、あまり調子がよくないので本日は欠席させていただきます
●明確な症状はありませんが、登校が難しい状態のため本日はお休みいたします
●疲れがたまっているので、体調管理のため本日はお休みさせていただきます
●体力・気力の回復のため、1日お休みをいただきます
明確な理由がなくても、「行けない」と感じるときは誰にでもあります。そんなときは、正直に伝えつつも、必要以上に言い訳をしなくて大丈夫です。1日休んでリセットすることで、また前向きに登校できることもあります。
長期的に学校を休む理由・言い訳の例文
本来であれば、学校はできるだけ休まず通うのが理想です。しかし、心や体の不調が続いていたり、生活環境が不安定だったりすると、1日だけでは回復しきれず、もう少し休みたいと感じることもあるでしょう。
毎日その都度、休む理由を考えるのがつらいときは、少し長めに休みたいという気持ちを素直に伝えることも一つの方法です。ただし、あくまで「学校に通いたいけれど今はしんどい」という前提であり、安易に長期間サボって学校に行かないことはおすすめしません。
●体調不良が続いており、しばらく安静にするよう医師から指示を受けています
●家庭の事情で生活環境が安定せず、登校が難しい状況です
●心身のバランスを崩しており、回復のため当面の間お休みをいただきます
●現在、登校に不安があり、少しずつ環境を整える時間をいただきたいです
もし「医師の指示」や「家庭の事情」など他の人を理由に含める場合は、事実と異なる内容を使わないように注意が必要です。保護者ときちんと話し合ったうえで、無理のない伝え方を考えましょう。
どんなにしんどくても、ずっと一人で抱えこむ必要はありません。「今は休みたいけど、また元気になったら通いたい」そういう気持ちを大切にしてください。
関連記事:学校が辛い人へ|不登校でも大丈夫!環境を変える選択肢を紹介|通信高校生ブログ|明聖高等学校
学校を休む理由を親に伝える5つのコツ
ここまでは、学校の先生に休む理由を伝えるための例文を紹介しました。しかし、本当の難関は、保護者に学校を休む許可をもらうときです。
そこで、学校を休む理由を保護者に伝えるときに押さえておきたい5つのコツを紹介するので、参考にしてみてください。
正直に気持ちを話そう
「1日だけでいいから学校を休みたい」という気持ちを、正直に話すことが大切です。「怒られるかも」「絶対許してくれない」など、思うところはあるでしょうが、以下のようにありのまま伝えてみましょう。
●「調子が悪いから、今日だけ休みたい」
●「午前中は部屋で勉強をして、午後からゆっくり学校のことを考えるから、今日だけ休みたい」
●「明日から学校に行けるように、今日は休んで充電したい」
もし、学校に行きたくない理由がはっきりしているのであれば、話してしまうのもひとつの手です。お家の人が忙しいタイミングだとゆっくり話を聞けないため、余裕を持って切り出してみてください。
タイミングを見て「ながら」で伝えよう
何かをしながら提案すると、提案が通りやすくなる「ランチョンテクニック」という方法があります。ご飯を食べながら、洗濯物をたたむ手伝いをしながら、散歩しながら、など保護者と一緒に何かをしながら、以下のように正直な気持ちを話してみましょう。
●「今日の卵焼きもおいしいね!ところで今日の学校なんだけど、1日だけ休めないかな?少し疲れていて、ゆっくりしたいんだ」
● 「歩きながら聞いてほしいんだけど、明日の学校を休みたいんだ。理由は、学校で嫌なことがあって。学校に行ったらまた嫌な思いをしそうなんだ。」
必ず提案が通るとは限りませんが、保護者が話を聞いてくれやすくなります。
休みたい期間を伝えよう
「1週間だけ」「1日だけ」など、休みたい期間をはっきりさせて伝える方法もあります。以下は、例文です。
●「今日、1日だけ学校を休めないかな?調子が悪くて……。」
●「明日から2日間だけ休めないかな?金曜日は頑張って行くつもり。休み中は、自分で教科書を進めるから心配しないで。」
保護者は、1日だけ休むことを許すと、何回も同じように休むのではないかという不安を感じます。はっきりと期間を伝えることで「1日だけならいいか」と思ってもらえる可能性が高まるのです。
また、行動心理学のテクニックである「ドア・イン・ザ・フェイス」を使って伝えると、要求が通りやすくなる効果を期待できます。自分の希望を通すために、あえて大げさな要求を断らせたうえで、本当の気持ちを伝えるテクニックです。
例えば、1日だけ休みたいときは、あえて「1週間休みたい」と伝えます。相手に「1週間は長すぎる」と要求を断られたらチャンスです。「それじゃあ、1日だけならどう?」と本当の要求を伝えると「1日だけならいいよ」といってもらえる可能性が高まります。
休み中の過ごし方も伝えよう
休んでいる間にゲームばかりしていると、お家の人に「サボりたかったんだ」と思われてしまいます。そのため、やるべきことややりたいことをあらかじめ伝えておくことが大切です。
例えば、以下のような伝え方があります。
●「1日だけ休ませてほしい。午前中は自分で勉強をして、午後はお風呂掃除をしてからゆっくり過ごすよ。」
●「明日から1週間学校を休みたい。休んでいる間に勉強が遅れないように、自分で教科書を進めるつもり。あとは、お家の手伝いもするから。」
●「学校に行きたくないから、休みたい。休んでいる間に、なんで行きたくないのか気持ちを整理して伝えるから、時間をちょうだい。」
関連記事:不登校の間、何をすればいい?おすすめの家での過ごし方|通信高校生ブログ|明聖高等学校
先生にも手伝ってもらおう
「自分では伝えにくい」「絶対に親が許してくれない」などの場合は、学校の先生から保護者に伝えてもらう方法もあります。
先生にお願いするときは、以下の例文を参考にしてみてください。
●「先生、実は学校を休みたいと思っているんですけど、自分では親にいえないので力を貸してもらえますか?」
●「学校を休んで心を休めたいのですが、親が許してくれなさそうで……。先生から、親に電話してもらえませんか?」
ただし、うまくいくかどうかは、先生次第です。先生との信頼関係ができていないと、難しいでしょう。信頼できる先生がいる場合は、最後の手段として試してみてください。
休み中に考えたい4つのこと
学校を休めることになったら、ゆっくりと休むほかに、なんとなく休みたくなった理由を探ってみることをおすすめします。このとき、以下の4つのポイントを踏まえて、自分と向き合ってみてください。
なぜ休みたいのかを考えよう
「なんとなく休みたい」「精神的に疲れている」と思った人は、なぜ休みたいと思ったのか、原因を探ってみるのが大切です。
以下のように、学校に対する不安や行きたくない理由をすべて書き出してみましょう。
●友達とトラブルがあった
●教室に入りにくい
●クラスメイトに嫌われているような気がする
書き出したら、内容を見て、自分で解決できるのかどうかを整理します。
信頼できる人に相談しよう
お家の人や兄弟など、信頼できる人に学校に行きたくない気持ちを相談してみましょう。もし話せるのであれば、なぜ行きたくないのか、理由まで話してみてください。
自分でも理由がわからない場合は、相談するなかで自分の気持ちに気づくことも多いです。
信頼できる人に相談しても解決が難しそうなときは、スクールカウンセラーに頼る選択肢もあります。
以下のサイトでは、悩みを解決するためのヒントを紹介しているので、参考にしてみてください。
あなたはひとりじゃない|内閣府 孤独・孤立対策推進室
登校方法や休み方を考えよう
信頼できる人と相談しながら、今後の登校方法や休み方を考えてみましょう。
例えば「あと1週間はゆっくり休む」「保健室登校ができるかどうか相談してみる」などがあります。
登校方法を考える場合は、学校の協力が必要です。担任の先生ではなくてもいいので、お家の人の力を借りながら、信頼できる先生に相談してみてください。
学校以外で学べる場所を探してみよう
学校以外にも、学習や体験活動をサポートしてくれる民間施設のフリースクールや習い事など、学べる場所はいくらでもあります。
学習の遅れが心配な場合は、学校以外で学べる場所を探し、居場所を増やしておくと安心です。
子どもが学校を休みたがるときの保護者の対応
ここからは、学校を休みたがるお子さんをもつ保護者の方に向けて、4つの対応方法を紹介します。「1日だけでも学校を休ませたら癖になるのでは?」と心配されている保護者の方は、ぜひ参考にしてみてください。
休みたい理由を丁寧に聴く
子どもが休みたいといったときは、理由を丁寧に聴くことが大切です。このとき嘘をつかせないように、理由がないなら理由がなくてもいいよという許容の姿勢を見せます。
もし「なんとなく休みたい」といっても、理由を否定したり怒ったりせず、まずは「休みたいんだね」と受容しましょう。
まずは1日だけ休ませる
学校を休みたがる頻度にもよりますが、基本的には1日だけ休ませる方法が有効です。
1日だけでも休ませてもらえると、子どもは安心できます。その結果、学校を休みたいときは、まず保護者に伝えるという習慣をつけることが可能です。
1日だけ休ませたあとも登校しぶりが続くなら、別の対応が必要です。
関連記事:子どもの登校しぶりとは?疑われる原因と保護者の対応の仕方|通信高校生ブログ|明聖高等学校
休み中の過ごし方や翌日以降のことを話し合う
学校を休むことを許可したあとは、休み中の過ごし方や翌日以降のことを話し合うことが大切です。また、1日の終わりに「休んでみてどうだったか」を確認すると、子どもの心の動きが見えてきます。
もし、次の日もまた休みたいといえば、なにか原因があると考えて対応しましょう。
関連記事:不登校は甘えじゃない!親ができる不登校になった子どもへの4つの対応|通信高校生ブログ|明聖高等学校
事前に休んでいい日数を決めておく
事前に休んでいい日数を決めておくのもひとつの手です。
例えば、1ヵ月に1回、1年に3回など、「理由なく休んでもいい日」という休暇制度を設けることで、子どもはいざというときに制度を使って休めます。
この方法なら、子どもは罪悪感を覚えたり、言い訳を考えたりせずに学校を休めるため、心の育成にもよいでしょう。ただし、家のなかの制度であることは十分に理解させることが大切です。
まとめ
学校を休むのは悪いことではありません。心身が疲れたときは、充電のために休むことも大切です。
ただし、学校を休みたいときは、正直な気持ちをお家の人に話す必要があります。本記事で紹介したコツを押さえながら正直な気持ちを話し、許可をもらってから休みましょう。
参考URL:
あなたはひとりじゃない|内閣府 孤独・孤立対策推進室
不登校の間、何をすればいい?おすすめの家での過ごし方|通信高校生ブログ|明聖高等学校
「学校に行きたくない」ときは無理しないで。休みながら自分に向き合う|通信高校生ブログ|明聖高等学校
学校が辛い人へ|不登校でも大丈夫!環境を変える選択肢を紹介|通信高校生ブログ|明聖高等学校
子どもの登校しぶりとは?疑われる原因と保護者の対応の仕方|通信高校生ブログ|明聖高等学校
不登校は甘えじゃない!親ができる不登校になった子どもへの4つの対応|通信高校生ブログ|明聖高等学校

明聖高等学校は、千葉・中野にキャンパスを構える通信制高校です。全日コース・全日ITコース・通信コース・WEBコースに分かれており、一人ひとりに合わせた高校生活を過ごすことができます。