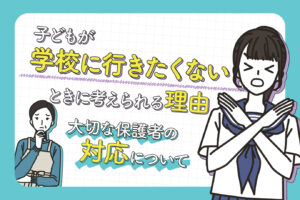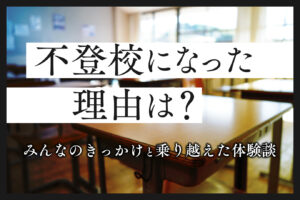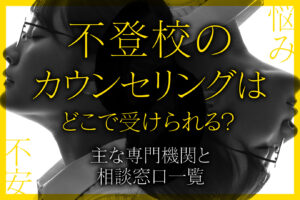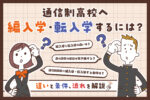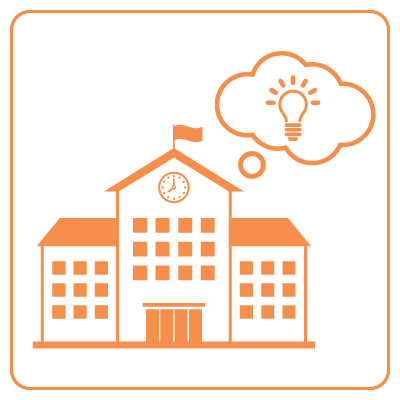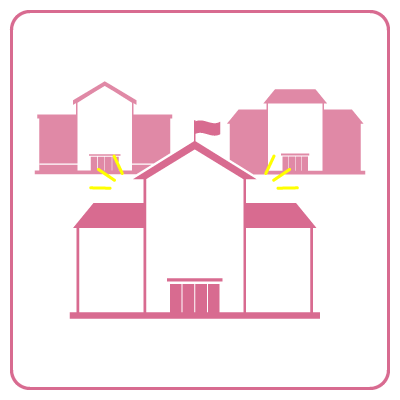「学校に行くのが辛い」と思いながらも、行かなければならないと無理をしている人もいるのではないでしょうか。学校での勉強は大切ですが、心や身体を壊してまで無理に通う必要はありません。
本記事では、学校が辛い人に向けて、原因と対処法や気持ちをやわらげる方法を解説します。思い切って環境を変えると問題が解決することもあるため、新たな選択肢も紹介します。
辛い気持ちを解消して、本来の自分を取り戻すために、最後まで読んでみてください。
1. 学校が辛いときは無理をしないことが大切!
心身の不調を感じながら無理に頑張り続けると、症状が悪化するおそれがあるため、学校が辛いときは無理をしないことが大切です。
まずは、登校頻度を落としたり、休んだりして、心身の回復を優先させましょう。少しエネルギーが回復したら、自分の心身の調子や気持ちと向き合って、どのような選択肢があるかを考えることをおすすめします。
「まだ頑張れる」「頑張らなくちゃ」と思っていても、心や身体は悲鳴を上げているかもしれません。頭痛や腹痛などの症状や、以前よりネガティブな気持ちが増えた場合は、いったん学校から離れてみてください。
2. 学校が辛いときのストレスの原因と対処法
学校が辛い原因を解消できると、辛い気持ちがやわらぐことがあります。ここでは、学校が辛いときのストレスの原因と対処法を大きく4つに分けて紹介します。
2.1. 体調が悪い
病気や生理などで体調が悪いと、学校に行くのが辛くなります。
例えば、過敏性腸症候群のように学校生活に支障が出る病気もあるため、症状が気になるのであれば、早めに医療機関を受診して医師の指示を仰ぐことが大切です。
すぐに改善が難しい病気の場合は、休み休み学校に登校したり、保健室登校をしたりといった選択肢も考える必要があります。
なお、心に大きなストレスがかかっているときも、頭痛や腹痛などの身体症状があらわれることがあります。病院に行っても原因がわからず、仮病を疑われることもあるかもしれません。
「自分は心の調子が悪いのかもしれない」と考え、ストレスの原因を探ってみてください。原因がわかれば、対処方法もわかるはずです。
ただし、原因がわからないこともあります。その場合は、身体の調子が戻るまで休むことを優先させましょう。身体の調子が戻ると、心も少しずつ元気になります。
2.2. 勉強が難しい
「学校の授業についていけない」「勉強が難しくて理解できない」と感じている人にとって、勉強する時間が長い学校は、辛い場所になりがちです。
勉強がわかるようになるために挑戦することも大切ですが、自分のペースやレベルに合わせて学ぶことも必要です。
あまりにもレベルがかけ離れていると感じるのであれば、環境を変えることも検討してみましょう。ただし、これは自分だけの力では難しいため、学校やお家の人の協力が必要です。
まずは、勉強について悩んでいることを信頼できる人に相談して、環境を変える方法を一緒に探してもらってください。
2.3. 生活習慣が乱れている
生活習慣が乱れると、心身の調子が悪くなり、学校に行くのが辛くなります。
夜寝るのが遅くて寝不足が続いたり、朝ごはんを食べずに登校したりと、不健康な生活は成長期のみなさんの心身のバランスを崩してしまうのです。
生活習慣の乱れに心あたりがある人は、夜決まった時間に寝るように心がけ、土日も同じ生活を送りましょう。また、1日3食しっかり食べて、十分に栄養をとることも大切です。
1人で改善できないことも多いため、お家の人に協力してもらいましょう。
2.4. 人間関係に悩んでいる
学校での人間関係に悩んでいる場合は、学校に行くのが辛くなります。
例えば、友達とうまくいっていなかったり、自分だけ仲間外れにされていたり、学校ではさまざまなことが起こりますよね。先生との相性が悪くて、いつも怒られてばかりという人もいるかもしれません。
人間関係の問題は、自分だけでは解決ができないため、まずは距離を置いて心身の回復を優先することが大切です。
エネルギーが回復してきたら、その環境のまま頑張れる方法を探るか、学校を変える選択肢を考えてみましょう。
3. 学校が辛い気持ちをやわらげる方法
辛いけど学校に通い続けたい気持ちを持っている人もいるはずです。少しでも辛い気持ちをやわらげられるように、3つの方法を紹介します。
3.1. だれかに相談する
自分の気持ちと向き合える状態であれば、だれかに相談して、ストレスの原因を突き止めたり解決策を考えたりするとよいでしょう。
お家の人や友達など、信頼できる人に相談するのが望ましいですが、難しい場合は次の相談先を利用する方法もあります。
| 相談方法 | 例 |
|---|---|
| SNS | ・こころのほっとチャット ・生きづらびっと ・あなたのいばしょチャット相談 |
| 電話 | ・チャイルドライン ・いのちの電話 ・こどもの人権110番 |
| 相談窓口 | ・教育相談センター |
相談窓口は、地域によって異なります。以下のページから近くの窓口を探してみてください。
3.2. 学校以外の居場所を見つける
学校以外に居場所があれば、そこでストレスを解消したり、勉強をしたりも可能です。
例えば、次のような場所があります。
- ● フリースクール
- ● 塾、習い事
- ● 支援センター
学校だけがあなたの居場所ではありません。ほかに居場所があれば、辛い気持ちが解消されることがあります。
ただし、子どもが一人で利用する場所として適切かどうかは考えなければなりません。お家の人と相談して、安全で安心できる居場所を見つけましょう。
3.3. 登校頻度を減らす
学校が辛い気持ちをやわらげるために、登校頻度を減らすことも効果的です。
休養をとっている間は、焦ったり不安を感じたりするかもしれませんが、自分で勉強を進めながらエネルギーが回復するのを待ちましょう。
エネルギーが回復してきたら、少しずつ登校頻度を増やしてみます。そのなかで、自分の気持ちと向き合い、ストレスの原因を解消していくことが大切です。
4. 今の学校が辛いなら新しい学校への転入学・編入学も考えよう
どんなに頑張っても、今の学校の辛さをやわらげられないこともあります。そのときは、新しい学校への転入学・編入学も考えてみましょう。今の学校以外に選択肢があるとわかっただけでも、気持ちが軽くなるはずです。
4.1. 特認校・不登校特例校への転入学【小中学生向け】
小中学生のみなさんは、特認校や不登校特例校を新しい学校の選択肢として考えてみてください。
| 学校の種類 | 特徴 |
|---|---|
| 特認校 (小規模校特別認可制度) |
・条件を満たすと校区外から転校できる学校 ・自然豊かな環境にある小規模校が多く、のびのび学校生活を送れる |
| 不登校特例校 (学びの多様化学校) |
・不登校の児童生徒が安心して元気に学べるように、特別な教育課程が組まれた学校 |
どちらの学校も、現在通っている学校からの転入学・編入学が可能です。
不登校特例校は数が少なく、住んでいる場所から通えないかもしれません。しかし、最近はオンライン授業を取り入れている場合も多く、学校に通わなくても授業を受けられる可能性があります。
まずは選択肢として特認校や不登校特例校を調べてみて、実際に転入学・編入学できるかどうかを学校に問い合わせてみるとよいでしょう。
4.2. 通信制高校への転入学・編入学【高校生向け】
高校生の場合は、通信制高校への転入学・編入学によって環境を変えられます。
通信制高校は、オンライン授業や自宅学習を通じて単位を修得し、高校卒業資格を取得できる高校です。全日制とは違って、毎日登校しなくてもよいコースが多く、自分のペースで学校生活を送れます。
例えば、千葉県の通信制高校である明聖高校のWEBコースは、年に3~4回の通学とオンライン学習で必要な単位を修得できます。エネルギーが回復したら、登校頻度を増やしたり、全日コースに変更したりも可能です。
まずは、現在の高校を退学せずに、通信制高校を調べてみてください。通信制高校に転入学すれば、これまで頑張って修得した単位を引き継げるはずです。
5. 不登校になったらどうする?学校を休ませるのが心配な保護者の方へ
お子さんが不登校になったとき、長期間学校を休ませるのが不安な保護者の方もいらっしゃると思います。
「このまま学校に行けず引きこもりになってしまうかも」「毎日ゲームばかりで本当に回復しているの?」など、お子さんの将来が心配だからこそ、さまざまな考えが頭を過りますよね。
大前提として、学校は行かなければならない場所ではありません。そのため、学校に行くことで心身の不調が起こるのであれば、休ませることが大切です。
不登校になったあとは、学習の進度や将来の進学に対する不安があるのは当然ですが、まずはお子さんの心身の健康を優先しましょう。
最近は、自宅にいてもさまざまな学習サポートを受けられるため、活用すれば学習の遅れも防げます。
保護者の方にとっては、根気のいる期間ですが、お子さんのエネルギーが回復するのを待ってから、将来のことを考えてみてください。
6. 学校が辛い子ども支えたい保護者が気をつけたいポイント
学校が辛い子どもをサポートしたいと考えている保護者の方は、4つのポイントに気をつけて接してみてください。これができれば、自宅がお子さんにとって安心できる居場所となるはずです。
6.1. 厳しい声かけをしない
まずは、親や他の家族から、強く励ましたり厳しい指導をおこなったりしないことが大切です。
不登校のお子さんは、心身が疲れており休息が必要です。
エネルギーがない状態で強いアプローチを受けると、焦ったり罪悪感が強まったりと、お子さんにとって負担となってしまいます。
強く厳しい言葉は不要と心得て、子どもの現在の状態を受け入れましょう。
6.2. 話しやすい雰囲気をつくる
わが子が不登校ともなれば、親としては「原因は何か」と考え、問い詰めたくなるかもしれません。
しかし、お子さん自身が悩みやストレスの原因を話し出すまで待つことも大切です。もしかすると、子ども本人ですら不登校の明確な原因がわからないのかもしれません。
いずれにしろ、お子さんに「親はあなたの味方」だと伝え続け、相談してもらえる雰囲気をつくることが大切です。
6.3. 家のなかで安心して過ごせる居場所をつくる
お子さんの心身を回復するためには、できればお子さんがひとりになれる部屋を確保できるとよいでしょう。
自由に使える場所があれば、子どもは自分自身を振り返ったり、趣味を楽しんだりできます。
もちろん、子どもをずっとひとりにするばかりではなく、親や家族からの継続的な働きかけも忘れずにおこないましょう。
6.4. 息抜きができるよう環境を整える
お子さんが息抜きをするためには、友人と連絡をとったり、遊んだりを勧めることも大切です。
不登校だからといって、遊びに行ってはいけないわけではありません。仲間と遊ぶ機会は、不登校から脱するきっかけづくりに役立ちます。
現在の学校に信頼できる友人がいない場合は、児童相談所や自治体がおこなうイベントに足を運び、出会う場をつくる方法もあります。
不登校になった子どもに親が取るべき対応について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
まとめ
学校が辛くて、心身に症状が出ているときは、無理をせずに休むことが大切です。学校と距離をとってエネルギーを回復しつつ、自分の気持ちと向き合ってみましょう。そのなかで、ストレスの原因がわかれば、対処法も明らかになるはずです。
もし、今の学校では問題が解決できないのであれば、学校を変える選択肢も考えてみてください。環境をガラリと変えることで、辛い気持ちから解放されることがあります。新しい学校として、小中学生は特認校や不登校特例校、高校生は通信制高校を調べてみましょう。
参考URL
学校に行くのがつらいなと感かんじたとき|こども家庭庁
相談窓口をさがす|こども家庭庁
WEBコース|明聖高等学校
不登校は甘えじゃない!親ができる不登校になった子どもへの4つの対応|通信高校生ブログ|明聖高等学校

明聖高等学校は、千葉・中野にキャンパスを構える通信制高校です。全日コース・全日ITコース・通信コース・WEBコースに分かれており、一人ひとりに合わせた高校生活を過ごすことができます。