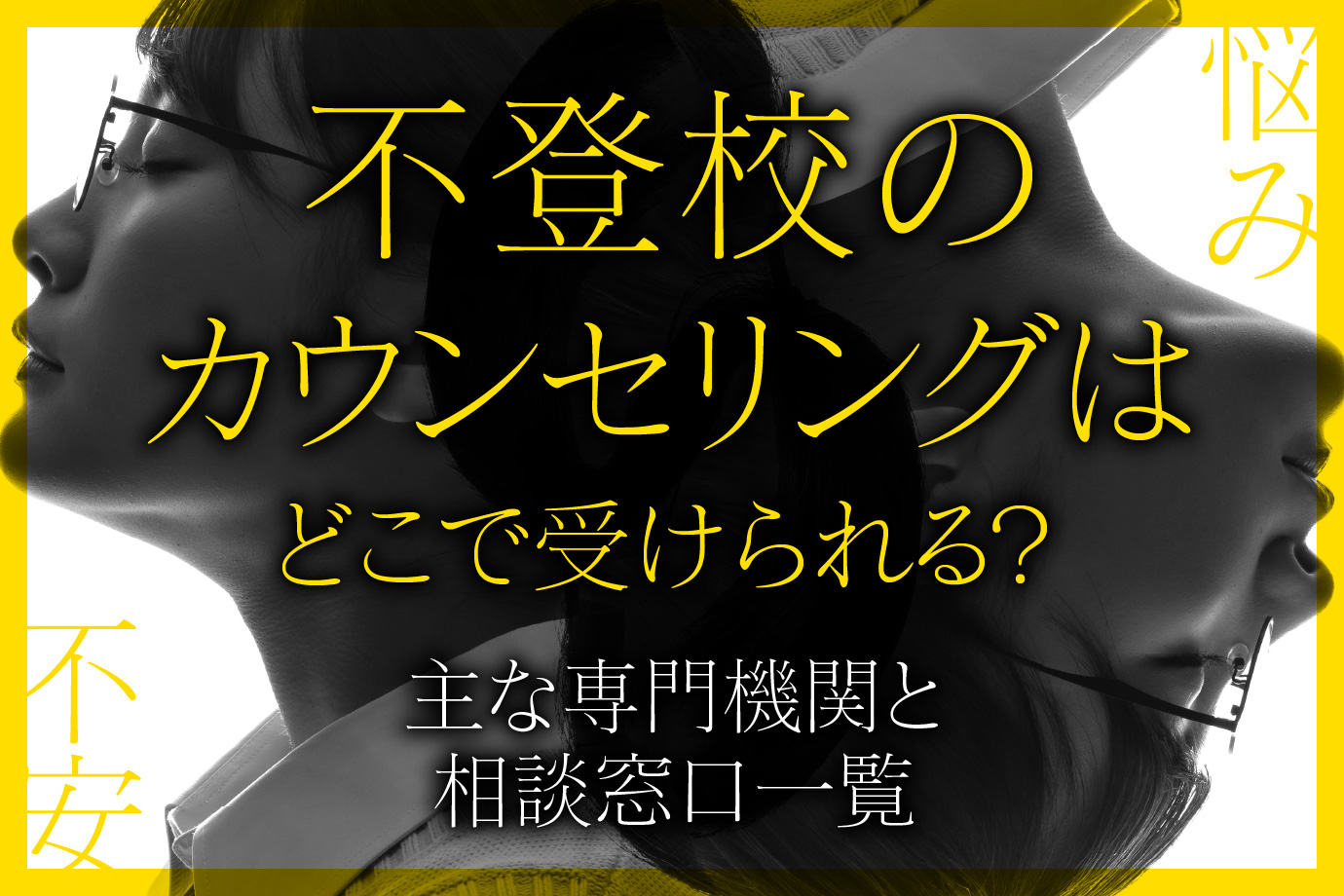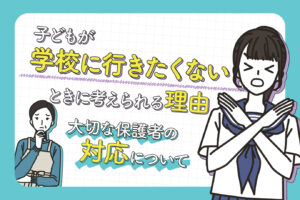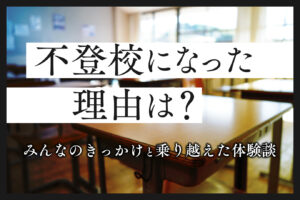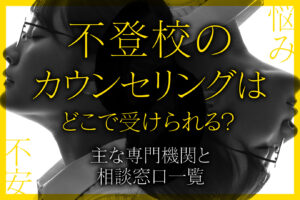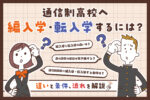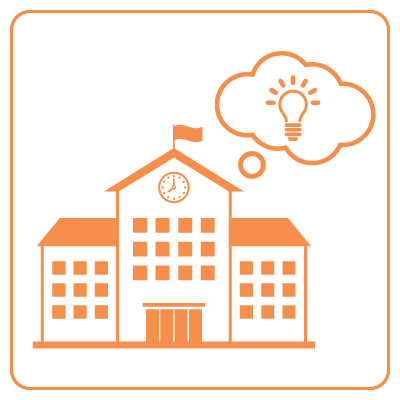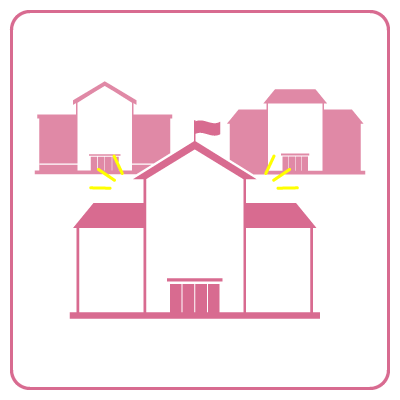不登校は、本人と家族だけでは解決が難しいことも少なくありません。
「不登校はダメなことだから、相談するのは恥ずかしい」(本人)、「家庭の問題は家庭内で解決しなければいけない」(保護者)といった理由で、第三者への相談をためらってしまうこともあるかもしれませんが、無理に家庭の中だけで対処しようとすると、場合によっては不登校が長引いたり、不登校を繰り返したり、保護者まで心身の健康を損なってしまったりする恐れもあります。
専門家のカウンセリングを受けたうえで、適切な対応方法を取ることが必要なケースもあるのです。
ここでは、不登校の悩みを相談し、カウンセリングを受けられる主な窓口や専門機関の一覧やそれぞれの特徴、効果的な活用方法について解説します。
不登校に対するカウンセリングの効果とは
不登校の我が子に対してカウンセリングが必要なのかどうか、判断できない保護者もいると思います。そこで、カウンセリングの効果について以下の3つの観点から解説します。
・子どもが「わかってもらえた」と思える
・ストレスへの対処方法が見える場合がある
・子どもとの接し方やサポートの仕方を助言してもらえることがある
子どもが「わかってもらえた」と思える
「だれにもわかってもらえない」とふさぎ込みがちな不登校の親子にとって、第三者による理解を得られることで、心の負担を軽減する効果を期待できます。
カウンセリングでは、子どもや保護者が不登校に関する悩みをカウンセラーに話します。カウンセラーは、気持ちや状況を理解しながら話を聞いてくれるため、終わったあとに子どもが「わかってもらえた」と思えるのです。
ストレスへの対処方法が見える場合がある
カウンセリングは、ただ話を聴くだけではなく、認知行動療法をはじめとする心理療法を活用して子どもの症状や行動にアプローチします。認知行動療法とは、当事者の考えや行動のクセを明らかにし、別の方法や心の負担が軽くなる方法を見つけていく心理療法です。認知行動療法を受ける過程で、現在抱えているストレスに対する対処法を学べることがあるのです。
子どもとの接し方やサポートの仕方を助言してもらえることがある
カウンセリングでは、子どもと保護者が個別にカウンセラーと話す機会があります。第三者としてカウンセラーが子どもの話を聴いたうえで、保護者に子どもとの関わり方について助言してくれることがあるのです。我が子との関わり方がわからなくなっている、どのように対応したらよいかわからないという保護者の方にとって、新たな道が開かれる可能性が期待できます。
不登校について相談できる窓口・専門機関一覧
不登校になると、本人も保護者も苦しくなりますが、不登校自体は決して悪いことでも、劣っていることでもありません。早期に根本的な解決へ向かうためには、気後れすることなく、状況に応じて専門家の力を借りることが必要です。
本人や保護者が相談できる、あるいはカウンセリングを受けられる窓口や専門機関は、大きく5つあります。
・学校
・公的機関
・民間施設
・医療機関
・メンタル・フレンド
メリット・デメリットも含めて紹介するので、状況に応じて選んでみてください。
学校
学校は、担任や養護教諭、スクールカウンセラーに相談できます。
メリット
学校での本人の様子を把握したり、学校復帰に向けた具体的な対応を検討したりするために、担任をはじめとした学校との連携は不可欠です。保健室・相談室登校の可否や人間関係への対処、柔軟な授業の受け方への対応など、より実際的な解決策について相談できます。
スクールカウンセラーは、小・中・高校生のメンタルヘルスの専門家として、本人の話にしっかり耳を傾けてくれ、アドバイスをしてくれます。在籍校と連携しやすいのもメリットです。
デメリット
教員個人の力量や学校の運営の在り方によっては、本人の状況を十分に把握してもらえていなかったり、効果的な対処をしてもらえなかったりする場合もあります。
傾聴に徹するスクールカウンセラーの場合は、相談が具体的な解決策につながらないこともあります。
公的機関
公的機関には、以下があります。
・ひきこもり地域支援センター(都道府県、指定都市)
・教育相談センター(都道府県・市区町村)
・児童相談所(都道府県)
・保健所(都道府県、指定都市など)
・24時間子どもSOSダイヤル(文部科学省)
・ヤング・テレホン・コーナー(警視庁)
・子どもの人権110番(法務局)
このうち、身近にある、ひきこもり地域支援センターと教育相談センターの特徴は以下が挙げられます。
| 公的機関 | 特徴 |
|---|---|
| ひきこもり地域支援センター | 社会福祉士、精神保健福祉士、臨床心理士などの専門家が在籍し、不登校やひきこもりの相談を無料で受け付けている |
| 教育相談センター | ・教育相談員や発達相談員(心理・福祉)などの専門家が、教育や子育ての観点から無料で相談に乗ってくれる ・不登校からの学校復帰を支援する適応指導教室(教育支援センター)の利用窓口になってるケースも見られる |
メリット・デメリットは、以下のとおりです。
メリット
| 公的機関 | メリット |
|---|---|
| ひきこもり地域支援センター | 地域におけるひきこもり支援の連携拠点となっているため、医療機関や民間の不登校支援施設を紹介してもらえることもある |
| 教育相談センター | 適応指導教室に通所して、学習支援や集団活動などの指導を受けた際には、学校の出席として扱ってもらえる場合がある |
デメリット
| 公的機関 | デメリット |
|---|---|
| ひきこもり地域支援センター | 具体的な活動支援を直接受けられないセンターも見られる |
| 教育相談センター | 特に適応指導教室は在籍校への復帰を前提としているため、本人が焦らされていると感じる恐れもある |
民間施設
民間施設には、以下があります。
・カウンセリング施設
・フリースクール
・キッズひまわりホットライン
・チャイルドライン
このうち、不登校に対する支援をより期待できるカウンセリング施設と、フリースクールのメリット・デメリットは以下のとおりです。
メリット
| 民間施設 | メリット |
|---|---|
| カウンセリング施設 | ・カウンセリングを通じて、子どもが心のストレスを軽減しながら、前向きなエネルギーを取り戻せることが期待できる ・不登校の解決にとどまらず、幅広く子どもの自立を支援してもらえる場合もある |
| フリースクール | ・必ずしも学校復帰を目的としておらず、幅広く社会復帰に向けたサポートをおこなっている ・フリースクールでの学びを通じて子どもの視野が広がったり、フリースクールが子どもの居場所になったりするケースもある |
デメリット
| 民間施設 | デメリット |
|---|---|
| カウンセリング施設 | ・継続的な利用が経済的な負担になる可能性がある ・学校復帰は子どもの自発性にゆだねられていることもあり、具体的な解決策を提示してもらえない場合がある |
| フリースクール | ・利用には費用がかかる ・フリースクールの数自体がそれほど多くないことや、在籍校と連携できるケースが少ないこともある ・活動方針や運営方針が本人に合わない可能性もある |
医療機関
不登校で医療機関に相談する際は、精神科や心療内科が適しています。医療機関のメリット・デメリットは、以下のとおりです。
メリット
医学的なアプローチで、うつ病や発達障害、起立性調節障害などの心身の症状を治療してもらえます。
デメリット
担当医が必ずしも不登校に関して理解があるとは限りません。また、薬物治療をおこなう場合は、副作用が生じる可能性もあります。
これらの施設・機関は、不登校中の子どもの居場所になる可能性があります。詳しくは、以下の記事もご参照ください。
不登校になったとき、どんなところが居場所になる?さまざまな選択肢を考えてみよう
メンタル・フレンド
メンタル・フレンドとは、不登校で悩んでいる子どもたちの話相手になったり一緒に遊んだりして、成長を支援するボランティアです。メンタル・フレンドは、10歳以上30歳未満の年齢制限があり、子どもに近い若い世代の大人と関わることが可能です。子どもの目線で話し相手になってくれるため、子どもの心の負担を軽減できる可能性があります。各自治体の児童相談所や福祉局が主体となっており、ボランティアは児童相談所職員の助言や指導を受けながら活動することになっています。
メンタル・フレンドのメリット・デメリットは、以下のとおりです。
メリット
特別な資格を有していないごく一般的な第三者の大人が、子どもの友達として関わってくれるため、引きこもりがちな子どもによい刺激をもたらします。メンタル・フレンドと関わるなかで、他人とのコミュニケーションを学ぶことも可能です。
デメリット
メンタル・フレンドは、ボランティアとして登録した大人であるため、大学や会社などに通っています。メンタル・フレンドの都合で途中交代が発生するというように、信頼関係を築いても継続して利用できないことがあります。また、子どもと合わないケースもあるので、注意が必要です。
不登校の相談窓口を上手に活用するために|保護者が子どもにできるサポート
専門機関や相談窓口を利用する際は、あくまで本人の意思に基づき利用することが重要です。子どもが「不登校について誰かに相談したい」「学校に行くために心の準備をしたい」といった想いを口にするようになったら、保護者は次のようにサポートしてみましょう。
・「どこに相談すればよいか」を相談する
・話し合いながら一緒に相談先を考える
・保護者だけで相談してみる
「どこに相談すればよいか」を相談する
適切な相談先を判断するために、まずは「どこに相談すればよいか」を保護者が支援窓口などに相談してみるとよいでしょう。相談先としては、学校の担任や、自治体の教育相談センター、その他の公的な電話相談窓口が考えられます。
話し合いながら一緒に相談先を考える
具体的な悩みの相談先は、本人と保護者がコミュニケーションを取りながら、一緒に考えてみましょう。その際には保護者の意見を押し付けてしまわないように注意が必要です。
保護者だけで相談してみる
もし、本人がなかなか第三者への相談に踏み切れないようであれば、保護者だけで相談してみるのも手です。相談してみた感想を子どもに伝えることで、利用の心理的ハードルを下げるとともに、自分に合っているかを判断してもらえます。
不登校のカウンセリングを受けられる場所を探す際の注意点
カウンセリングは、カウンセラーの技量によって効果が左右されるため、カウンセリングを受けられる場所を探す際は注意が必要です。カウンセラーのなかでも、民間資格のみをもったカウンセラーが個人で開設しているカウンセリングルームは、特に差があります。
カウンセラーとしての国家資格は、臨床心理士や公認心理師です。この資格を持つカウンセラーは、大学や大学院で心理学をはじめとする専門的な知識とスキルを習得し、実習経験を積んでいます。
不登校のお子さまに発達障害が疑われる場合は、国家資格をもった心理士でなければ検査できない点にも注意が必要です。
公的機関・医療機関ではなく、民間施設でカウンセリングを受ける際は、カウンセラーの資格にも注目してみてください。
明聖高校では専門資格をもった教員がサポートします!
通信制高校である明聖高校には、カウンセリングの資格を持った教員や専門のカウンセラーが常駐しています。いつでも相談できる環境が整っているため、悩みや不安を抱えながら学校に通いたいお子さまを手厚くサポートできます。
もし、不登校気味で高校進学に不安を抱えている場合は、全日制ではなく通信制高校を選択し、自分のペースで成長していく方法もあります。選択肢のひとつとして、明聖高校を検討してみてください。
不登校生徒へのサポート体制|明聖高校
まとめ
不登校に関する相談先やカウンセリングを受けられる場所には、学校はもちろん、公的機関や民間施設、医療機関など、さまざまな選択肢があります。本人や家庭の状況に合った相談先を選び、活用することで、納得のいく形で学校復帰・社会復帰できるでしょう。
もし、在籍校への復帰が難しそうな場合は、不登校支援をおこなっている通信制高校に相談してみるのもおすすめです。明聖高校では、各教員が「カウンセリング」や「メンタルヘルス」といった専門の研修を受講しており、不登校に悩む子どもに寄り添ったサポートができます。入学を具体的に検討していない状態でも相談を受け付けているので、もうひとつの相談窓口として検討してみてください。
参考URL:
不登校に関する実態調査 平成18年度不登校生徒に関する追跡調査報告書
「不登校問題」と親(保護者)のメンタルケア_通信制高校・高等専修学校選びのニュースク
子どもの不登校、どうすればいい?親ができる3つの大切なこと|うららか相談室
【まとめ】1人で悩むより相談してみて。不登校・子どもの悩み相談場所 – 不登校の原因・対策解説ノート

明聖高等学校は、千葉・中野にキャンパスを構える通信制高校です。全日コース・全日ITコース・通信コース・WEBコースに分かれており、一人ひとりに合わせた高校生活を過ごすことができます。