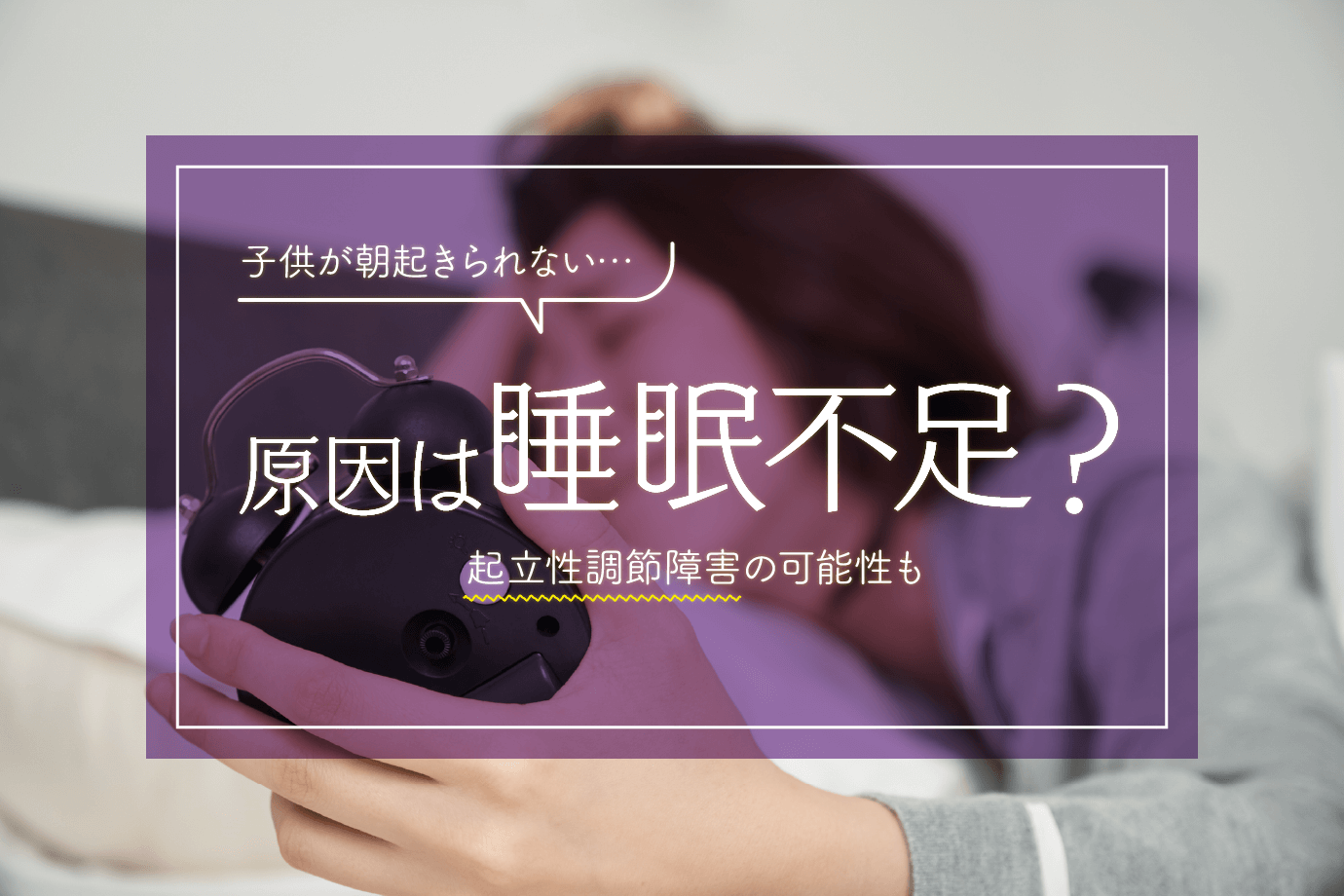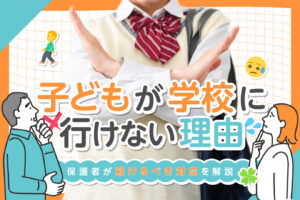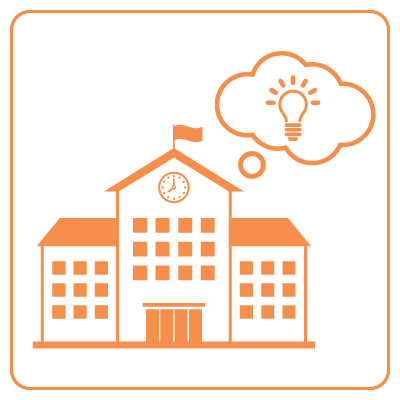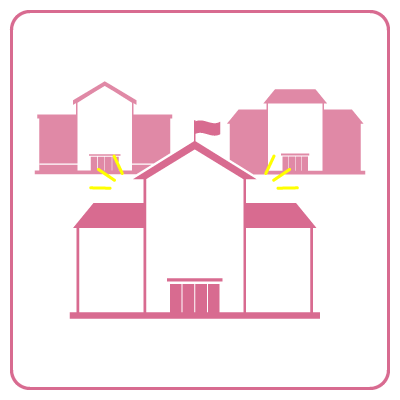子供が朝起きられないと学校に遅刻したり、授業に集中できず勉強がおろそかになったりしてしまいます。たまにそういった日があるぶんには問題ないかもしれませんが、いつも眠そうにしているのであれば、生活習慣に問題があるか、何らかの病気の可能性もあります。今回は子供が朝起きられない場合の対処法と、「起立性調節障害」という病気についてもご説明します。
子供が朝起きられない原因は?
子供が朝起きられない原因は、その子に必要な睡眠が十分にとれていないことが原因かもしれません。日本の子供は世界的にみても夜更かしであるといわれています。就寝時間を早くすることで朝起きやすくなるようなら、今よりも睡眠時間を多めに確保する習慣をつけましょう。
睡眠を十分にとっているはずなのに朝起きることができないのであれば、睡眠の質が低下しているか、もしくは「起立性調節障害」である場合も考えられます。起立性調節障害とは、自律神経系の異常で循環器系の調整が適切に行うことができない疾患です。
症状としては、「朝起きられない」「立ちくらみ」「疲れやすい」などがあります。もしも起立性調節障害であれば、病気ですので適切な対処が必要です。
こんな場合は要注意!夜更かしにつながる生活習慣
例えば、寝る直前までスマートフォンやパソコン、ゲームの画面を見続けていると、ディスプレイの光によって体内時計が乱れてしまって寝付きにくい状態になります。
親の帰宅が遅く、それにともなって夕食の時間が夜遅くなるのも夜更かしにつながる要因です。クラブ活動や習い事などをはじめることで帰宅が遅くなり、就寝時間が後ろにずれてしまうケースもあります。
また、人間は朝日を浴びることで体内時計を調整していると考えられています。しかし、朝起きられない子供は朝日を浴びることができませんので、「朝日を浴びることができない→体内時計を正常にリセットすることができない→夜眠れない」という悪循環に陥りやすいです。
睡眠不足の影響は?不登校につながってしまうことも
睡眠が十分にとれていないと、ぼんやりとした状態で登校し強い眠気をこらえたまま授業を受けることになります。眠気のため授業に集中できず勉強についていけなくなる場合もあるため、好ましい状況とはいえません。
また、文部科学省の「中高生を中心とした子供の生活習慣が心身へ与える影響等に関する検討委員会」の中で、就寝と学力の関係について「毎日同じくらいの時間に寝起きしている児童ほど、学力調査の平均正答率が高い傾向」「毎日朝食をとる児童生徒ほど、学力調査の得点が高い傾向」
という調査結果を公表しています。
さらに、睡眠不足は学力低下につながるだけでなく、不登校のきっかけになっていることも珍しくありません。不登校の継続理由にも「朝起きることができない」というものがあり、睡眠不足が与える悪影響が小さくないことがわかります。
生活習慣を見直そう!睡眠不足を解消するための対処法
① 適度な運動を習慣づける
睡眠不足を解消するためには、適度な運動を習慣づけることが有効です。適度な運動は入眠を促進し、中途覚醒を減らす効果があります。ただし、運動するタイミングは大切で、就寝直前に激しい運動をしてしまうとむしろ入眠を妨げてしまうため注意しましょう。
② 就寝前にスマートフォンやパソコンなどを使わない
スマートフォンやパソコンのディスプレイから発せられる光は体内時計を乱すため、就寝前にスマートフォンやパソコンを使わないようにしましょう。
③ 遅い時間にカフェインを摂らない
カフェインの摂取も入眠を妨げたり、睡眠を浅くしたりする可能性があります。カフェインの作用は3時間程度持続するため、遅い時間にコーヒーや紅茶、ココア、栄養ドリンクなどを飲まないことが大切です。
④ 早寝より早起きを意識。朝に日光を浴びて体内時計をリセット
また、睡眠習慣を適切な状態に保つには、「早寝」よりも先に「早起き」を習慣づけることがポイントです。最初のうちは就寝時間を早めても眠くなりにくい場合もあるため、早起きをして朝日を浴びることで体内時計を朝型へと移行していきましょう。
この際、ベランダなどに出て直接日光を浴びるのが望ましいですが、難しい場合は窓辺で顔を外に向けるだけでも大丈夫です。この習慣を2週間ほど続けることで子供の体内時計は徐々に朝型に変わり、早起きをつらいと感じなくなっていきます。
ただし、週末に遅くまで寝てしまうと体内時計が再び狂ってしまうため、休みの日であっても普段と変わらず早起きを続けることが大切です。
しっかり寝ても起きられない場合は起立性調節障害の可能性も
睡眠不足を解消しても状況が改善しない場合、起立性調節障害である可能性があります。心配である場合はかかりつけ医に事情を説明し、相談するとよいでしょう。
起立性調節障害の症状は、めまい、動悸、失神、疲れやすさ、腹痛、吐き気、食欲不振、朝起きられなくなるなど、人によってさまざまです。
また、自律神経系の病気であるため心の影響を受けやすく、本人がストレスを抱えることは症状悪化の要因になります。しかし、起立性調節障害だとわからないうちは「怠けている」「仮病」と誤解されることもあり、周囲の誤解によって本人が深く傷つき、より症状が悪化してしまうこともあります。
もし、起立性調節障害の疑いがある場合は、なるべく早く小児科などを受診しましょう。病院のホームページなどを見て、起立性調節障害を扱っているところを受診するのがより確実です。
本人のつらさがわかってもらいにくいため、家族や学校関係者など周囲の人の理解が大切な病気です。
まとめ
睡眠不足による悪影響はさまざまですが、生活習慣を少し見直すだけで解消することもあります。単に夜更かしを注意するのではなく、子供が就寝しやすいような状況が作れるよう協力してあげるとよいでしょう。また、起立性調節障害の場合は、本人の頑張りだけではどうすることもできません。「うちの子はだらしないだけ」などと思わず、疑わしいときは積極的にかかりつけ医などに相談してみましょう。
参考URL
子どもの睡眠 | e-ヘルスネット(厚生労働省)
特集2 子どもの睡眠不足はなぜ悪い? 夜更かしっ子大国、日本 生活習慣病、イライラ、学力低下招く – 全日本民医連
厚生労働省 睡眠対策1 表紙_指針
睡眠不足や睡眠障害、子どもへの大きな影響 | e-ヘルスネット(厚生労働省)
中高生を中心とした子供の生活習慣が心身へ与える影響等に関する検討委員会 第1回 配付資料
日本小児心身医学会
起立性調節障害 (きりつせいちょうせつしょうがい) | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会

明聖高等学校は、千葉・中野にキャンパスを構える通信制高校です。全日コース・全日ITコース・通信コース・WEBコースに分かれており、一人ひとりに合わせた高校生活を過ごすことができます。