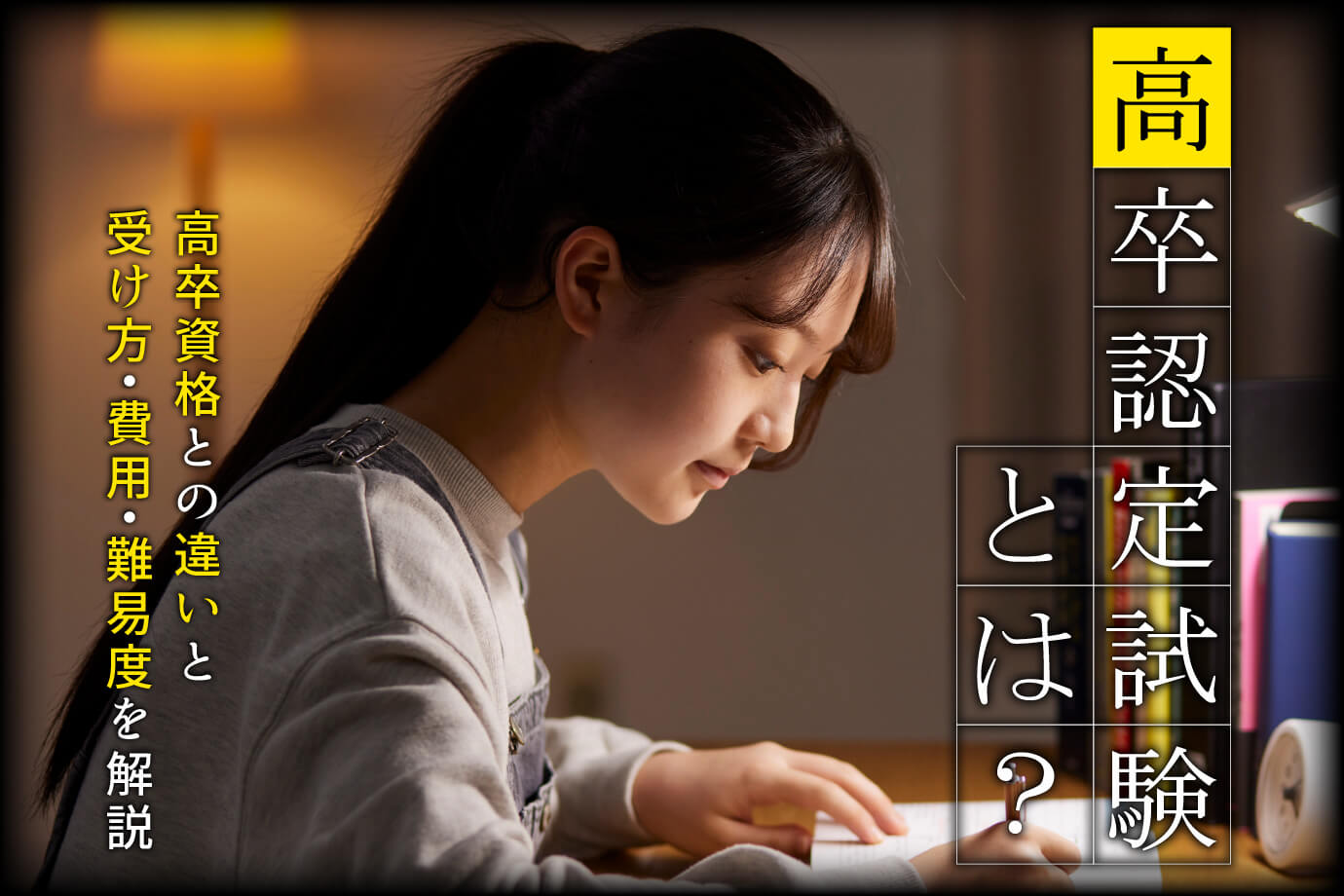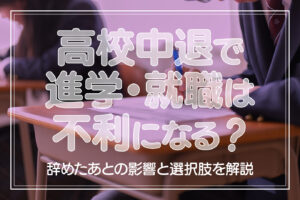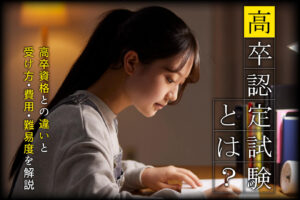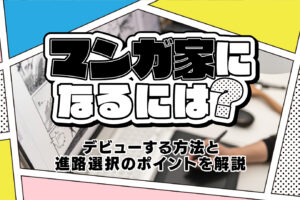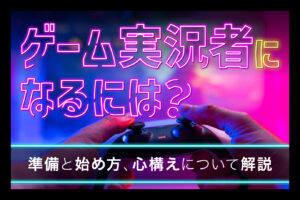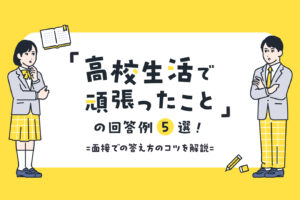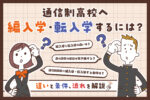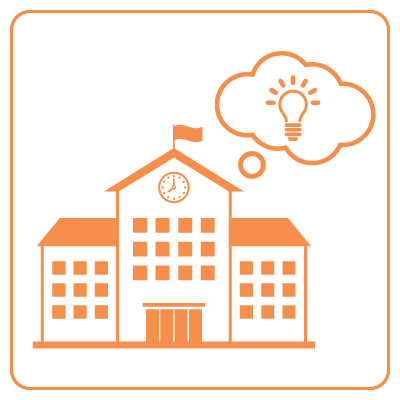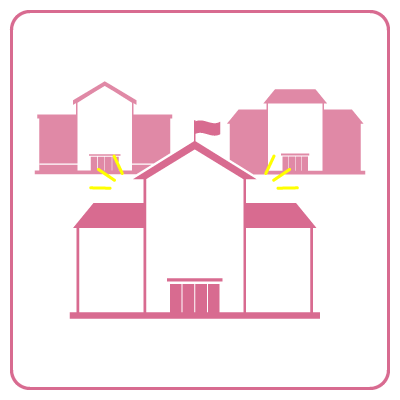高卒認定試験とは、高校卒業と同程度またはそれ以上の学力があるかどうかを認定する試験です。
高校を卒業できない場合でも、高卒認定資格を取得できれば、大学や専門学校、各種資格試験を受験できるようになります。また、高卒資格が必要な求人への応募が認められる場合もあり、進路選択の幅が広がります。
高校進学を迷っている人は、高卒認定と高卒資格のメリット・デメリットや取得方法などの違いを知ったうえで、慎重に選ぶことが大切です。
今回は、高卒認定と高卒のメリット・デメリットを紹介します。また、高卒認定試験の受け方・費用・難易度を解説するので、中学校卒業後の進路を考えるときの参考にしてみてください。
高卒認定試験とは?
高卒認定試験とは、簡単にいうと、合格すると高校を卒業していなくても高校卒業と同じ、またはそれ以上の学力を持っていると証明できる試験です。令和5年度は1万191人(※)が高卒認定試験を受験しており、不登校だった人や高校を途中でやめた人など、さまざまな人が挑戦しました。
文部科学省は、高卒認定試験について、以下のように説明しています。
高等学校卒業程度認定試験は、様々な理由で、高等学校を卒業できなかった方等の学習成果を適切に評価し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があるかどうかを認定するための試験です。合格者は大学・短大・専門学校の受験資格が与えられます。また、高等学校卒業者と同等以上の学力がある者として認定され、就職、資格試験等に活用することができます。
引用:高等学校卒業程度認定試験 概要・パンフレット等|文部科学省
高卒認定を取得できれば、高校を卒業していなくても、大学や短大、専門学校、資格試験を受験できるようになったり、就職の幅が広がったりします。
※ 参考:令和6年度高等学校卒業程度認定試験|文部科学省
高卒認定資格と高卒資格の違い
高卒認定資格と高卒資格の大きな違いは、最終学歴です。
| 資格の種類 | 取得方法 | 最終学歴 |
|---|---|---|
| 高卒認定資格 | 高卒認定試験に合格する | 中学校卒業(中卒) |
| 高卒資格 | 高校の卒業要件を満たし、卒業する | 高校卒業(高卒) |
高卒資格は、全日制・定時制・通信制などの高校を卒業したと証明する資格で、単位の取得や決められた日数の出席など、さまざまな卒業要件を満たさなければなりません。
最終学歴が違うと、求人数が変わります。令和5年度の求人数を見ると、以下のような違いがあり、高校新卒者と比べて中学新卒者は求人数が少ないとわかります。
● 高校新卒者の求人数:約44万4,000人(求職者数:約12万6,000人)
● 中学新卒者の求人数:706人(求職者数:677人)
参考:令和5年度「高校・中学新卒者のハローワーク求人に係る求人・求職状況」取りまとめ(7月末現在)|厚生労働省
求人数が少ないと職種や職場の選択肢が限られるでしょう。一方、高卒認定を取得していると、最終学歴が高卒と指定されている求人に応募できる場合があります。企業ごとに判断が違うため確認は必要ですが、高卒認定によって就職の幅が広がるはずです。
また、大学や専門学校など、高校よりも上の教育機関への受験資格を得られます。
中卒と高卒の違いは、以下の記事でも紹介しているので、参考にしてみてください。
内部リンク:中卒、中卒 就職(作成中)
メリットの違い
高卒認定と高卒資格のメリットには、以下のような違いがあります。
| 資格の種類 | メリット |
|---|---|
| 高卒認定 | ・大学や専門学校、各種資格の受験資格を得られる ・短期間で取得できる ・高校に通わなくても取得できる |
| 高卒 | ・大学や専門学校、各種資格の受験資格を得られる ・在学中に進路指導や受験指導を受けられる ・最終学歴が高卒になる |
高卒認定を取得すると、高校に通わなくても大学や専門学校を受験できるようになります。
中学校卒業後に働きたい人や自分のペースでゆっくり勉強したい人など、高校の卒業要件を満たすのが難しい人にとって、大きなメリットです。
高卒は、取得までに時間や労力がかかる一方、最終学歴が高卒となるため、進学や就職など進路選択の幅を広げたい人にとって有利に働きます。
デメリットの違い
高卒認定と高卒資格のデメリットには、以下のような違いがあります。
| 資格の種類 | デメリット |
|---|---|
| 高卒認定 | ・最終学歴が中卒になる |
| 高卒 | ・3年以上高校に在籍しなければならない ・74単位以上を修得しなければならない ・その他、高校が定める要件を満たさなければならない |
高卒資格は、3年間以上の在籍が難しい人にとって、取得しにくい資格です。
高卒認定は自分のペースで取得できる一方、最終学歴が中卒となるため、就職したい職種や進学したい大学・専門学校などによって、難易度が高くなる場合もあります。
高校進学に迷っている人は、それぞれのデメリットを知ったうえで、将来について慎重に考えてみてください。
高卒認定試験の試験科目
ここからは、高卒認定試験の内容を解説します。
高卒認定試験の試験科目は、以下のとおりです。
| 教科 | 科目 | 合格要件 |
|---|---|---|
| 国語 | 国語 | 必修 |
| 数学 | 数学 | 必修 |
| 外国語 | 英語 | 必修 |
| 地理歴史 | 地理 | 必修 |
| 歴史 | 必修 | |
| 公民 | 公共 | 必修 |
| 理科 | 科学と人間生活 | 選択 |
| 物理基礎 | ||
| 化学基礎 | ||
| 生物基礎 | ||
| 地学基礎 |
中学校を卒業後、高校に一度も通わず高卒認定試験を受ける場合、国語から公共までの6科目は必ず受けなくてはなりません。理科は選択制になっており、以下の選択肢からどちらかを選びます。
| 選び方 | (1) | (2) |
|---|---|---|
| 受ける科目 | ・科学と人間生活 ・物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎から1科目 |
・物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎から3科目 |
| 理科の科目数 | 2科目 | 3科目 |
理科の選び方によって科目数が変わり、全科目の合計は8〜9科目です。
ただし、高校に在籍中の人や途中で退学した人は、修得済み単位の認定で科目が免除されると、受験する科目数が少なくなります。
高卒認定試験の試験科目は、令和6年度の第1回試験から変更されています。試験科目を確認する際は、古い情報に気を付けましょう。
高卒認定試験の合格率と難易度
令和4年度と令和5年度の結果を見ると、合格率は45~47%程度で、半数近くが合格しています。
| 年度(※) | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 令和4年度(第1回) | 8,444人 | 3,796人 | 45.0% |
| 令和4年度(第2回) | 8,710人 | 4,165人 | 47.8% |
| 令和5年度(第1回) | 8,290人 | 3,948人 | 47.6% |
※ 高卒認定試験は、1年に2回おこなわれます。
参考:令和5年度第1回高等学校卒業程度認定試験実施結果|文部科学省
難易度は、中学生〜高校1年生程度の学力レベルとされているため、独学でも合格を目指せるでしょう。各科目は、100点満点のうち45〜50点前後で合格できることからも、難易度はそれほど高くありません。
ただし、人によっては受験科目が最大8~9科目となるため、広い範囲の勉強が必要です。
高卒認定試験の費用
高卒認定試験の受験料は、科目数によって以下のように違います。
| 科目数 | 受験料(※) |
|---|---|
| 7~9科目 | 8,500円 |
| 4~6科目 | 6,500円 |
| 1~3科目 | 4,500円 |
※ 令和6年度時点の受験料です
受験料は変わることがあるため、必ず受ける年度の受験料を確認しましょう。
高卒認定試験の受け方
ここでは、高卒認定試験の受け方を次の5つのステップに沿って解説します。
● 受験資格・条件を確認する
● 出願手続きをおこなう
● 受験票を受けとる
● 試験を受ける
● 結果を受けとる
全体の流れを知ってから準備をはじめると、見通しを持ってスムーズに受験までたどり着けるので、参考にしてみてください。
受験資格・条件を確認する
高卒認定試験の受験資格は、以下のとおりです。
・受験する年度内に16歳以上になる
・大学資格がない(中卒の人、高校を中途退学した人、高校に在籍しているが通学していない人)
ただし、外国で規定の課程を修了している人やその他要件を満たす人など、すでに大学入学資格を持っている人は、受験できません。
まずは、受験資格を満たしているかどうかを確認しましょう。
出願手続きをおこなう
高卒認定試験は、8月と11月におこなわれ、1年に2回、受験のチャンスがあります。
試験を受けるために必要な出願手続きは、4〜5月と7〜9月の間におこないます。ただし、年度によって日付が変わるため、必ず受験する年度の日付を確認しましょう。
出願手続きに必要な願書は、次の方法で入手できます。
| 願書の入手方法 | 詳細 |
|---|---|
| 直接とりに行く | ・文部科学省2階エントランス |
| ・各都道府県教育委員会 | |
| インターネットで請求する | こちらから |
受験票を受けとる
無事に出願手続きが完了したら、受験票が届くので受けとりましょう。受験票には、以下の項目が書かれているので、申請内容と間違いがないかを確認します。
● 試験日
● 試験会場
● 受験科目
もし、内容に間違いがあった場合、指定の期間内に受験票の裏に記載されている「お問い合わせ先」に連絡する必要があります。受験票が届いたらすぐに確認しましょう。
受験票の準備が整ったら、当日までに会場への行き方を決め、遅刻しないように計画を立ててみてください。
試験を受ける
高卒認定試験の当日は、試験開始の30分前までに会場に着いているようにしましょう。
出発前に持ち物を確認し、忘れ物がないように気を付けます。なお、服装は自由で構いません。
【持ち物】
● 受験票
● 受験科目決定通知書
● 試験会場案内図
● 筆記用具
● 時計(スマートフォンは不可)
● 財布
● スマートフォン、携帯電話
● 学習教材(テキスト、ノートなど)
● お昼ごはん、飲み物(日程による)
● 上履き(会場による)
当日までに受験票を失くしてしまった場合、会場で再発行の手続きができます。会場に向かう途中で忘れたことに気付いたのであれば、家に戻らず会場で再発行しましょう。
試験はマークシート式なので、わからない問題があっても必ず埋めるのが大切です。十分に力を発揮するために、前日はしっかり眠り、朝ごはんを食べて臨みましょう。
なお、証明書の発行時に受験票が必要なため、試験後も捨てずに保管しておいてください。
結果を受けとる
結果は、試験終了後1ヵ月程度をめどに、郵送で届きます。
| 種別 | 届く書類 |
|---|---|
| 合格者 | 合格証書 |
| 科目合格者 | 科目合格通知書 |
合格した科目は次回の試験で免除されるため、不合格だった科目に力を入れて再挑戦しましょう。
高卒認定試験の勉強方法
高卒認定試験の勉強方法は、大きく以下の3つに分けられます。
● 参考書・過去問を活用する
● スマートフォンアプリを活用する
● 通信講座・塾・予備校を利用する
自分に合った方法を選んで、合格を目指しましょう。
参考書・過去問を活用する
独学で高卒認定試験に挑む場合は、参考書や過去問を活用するとよいでしょう。過去問と解答は、以下のページから無料で見られます。
高等学校卒業程度認定試験問題(高卒認定試験) 解答・過去問題|文部科学省
スマートフォンアプリを活用する
最近は、高卒認定試験に特化したスマートフォン用学習アプリがあります。反復が必要な暗記科目の学習におすすめです。参考書・過去問と一緒に使うと、学習効果を期待できるでしょう。
通信講座・塾・予備校を利用する
独学が不安な人や学習時間が限られている人は、通信講座や塾、予備校の利用も検討してみましょう。独学よりも効率的に学べるうえ、わからない問題をその場で解決できます。
ただし、独学と比較して費用がかかる点には留意が必要です。
通信制高校なら自分のペースで「高卒資格」を取得できる!
高校に通うのが難しいという理由で高卒認定の取得を考えている人は、高卒認定のほかに、通信高校で高卒資格を取得する方法も検討してみてください。
自宅での自学自習で作成したレポートを先生に添削してもらったり、年数回程度の登校(スクーリング)で授業を受けたりして学習を重ねて単位認定試験に合格すると、高卒資格を取得できます。経済的な事情や時間の都合で全日制・定時制に通えない人や、毎日の通学が難しい人でも、先生やほかの生徒と交流を深めながら高校卒業を目指せます。
明聖高校のWEBコースは、インターネットを通じて登校する「オンライン登校」が可能です。自宅でのオンライン学習と、1年に4回程度の登校で必要な単位を修得できます。自分のペースでゆっくり学習を進めたい人や、スポーツや芸能活動などほかに優先したいことがある人におすすめです。
まとめ
高卒資格と高卒認定は、どちらも大学などの受験資格を得られますが、証明する内容や取得方法には違いがあります。社会では学力だけが評価されるわけではないため、自分にとって何が必要なのかをしっかり考え、高卒認定か高卒資格かを決めるのが大切です。高卒認定だけでなく、通信制高校や定時制など全日制高校以外の方法で高卒資格をとれないかも含め、さまざまな選択肢を検討してみてください。
参考URL:
高等学校卒業程度認定試験(旧大学入学資格検定)|文部科学省
高等学校卒業程度認定試験Q&A|文部科学省
大学入学資格について
令和5年度第1回高等学校卒業程度認定試験実施結果|文部科学省
令和5年度「高校・中学新卒者のハローワーク求人に係る求人・求職状況」取りまとめ(7月末現在)|厚生労働省

明聖高等学校は、千葉・中野にキャンパスを構える通信制高校です。全日コース・全日ITコース・通信コース・WEBコースに分かれており、一人ひとりに合わせた高校生活を過ごすことができます。