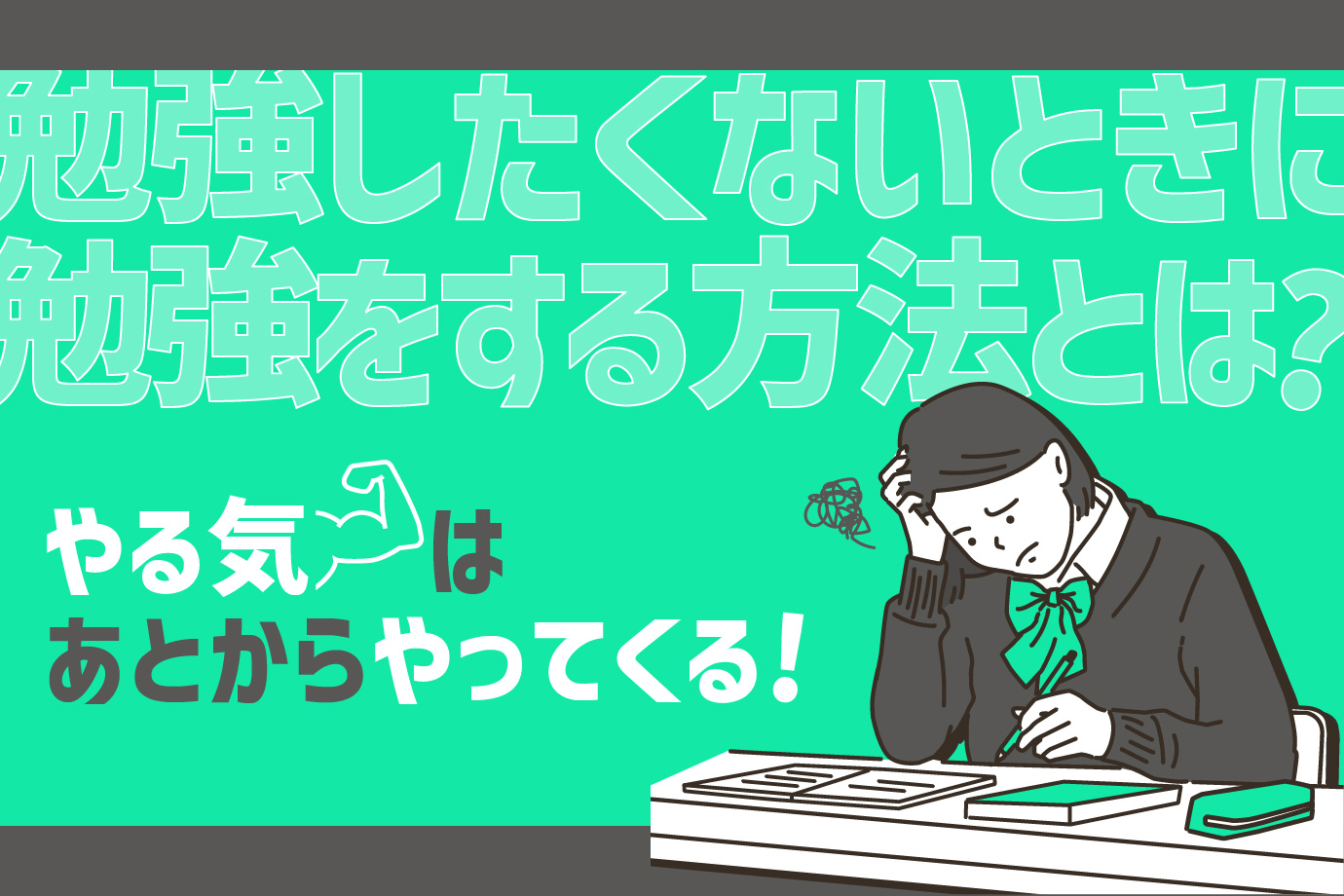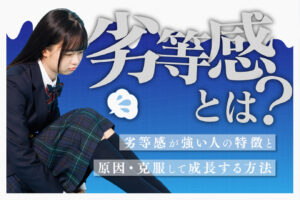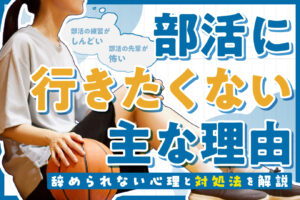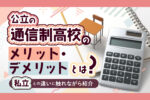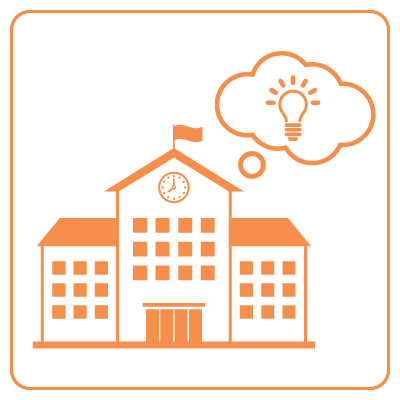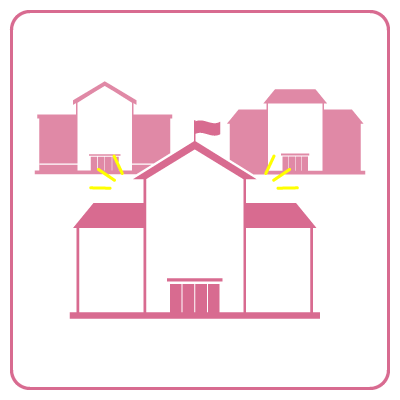学生のみなさんは、夏休み・冬休みの宿題やテスト前などで「勉強したくないけれど、やらなければ」と、やる気がないなかで勉強しなくてはならない状況に陥ることがあるのではないでしょうか。
「やる気さえ出ればなんとかなるのに」と思ってやる気を出す方法を探している人もいるはずです。やる気を出す方法を探すよりも、やる気がない状態でも勉強をスタートできる方法を身につけたほうが早く問題を解決できます。
そこで今回は、やる気の仕組みと勉強したくないときに勉強をはじめる方法を解説します。勉強になかなか手をつけられず困っている人は、この記事を読んで、まずはひとつ行動してみましょう。
勉強したくないときにやる気を出す方法はある?
勉強をしたくないときにやる気を出すためには、やる気に関する理論や脳のしくみを知っておく必要があります。
やる気に頼るのではなく、やる気がない状態からでも勉強をはじめられる方法を知っておくと、いざというときに役立ちます。
やる気と脳の関係
人間の脳では、さまざまな神経伝達物質が働いており、そのなかでもドーパミンがやる気に関係しています。
興味のあることやワクワクすることが起こったり想像したりすると、それが刺激となって脳内でドーパミンが放出されます。ドーパミンが放出されると、脳の報酬系と呼ばれる部位が活発化して気持ちがよくなります。これが、やる気がわいている状態です。
ドーパミンは、次のような場合で放出されやすくなります。
● 実現したらうれしいことを想像する
● 予想していなかったうれしいことが起こる
● ご褒美がもらえる状況で取り組む
これを応用して勉強をはじめると、やる気がわきやすくなるでしょう。
やる気は出すものではない
ドーパミンは、ある行動をきっかけとしてワクワクすると放出されることがわかりました。つまり、やる気がわくよりも先に行動しているのです。
アメリカの神経科学者であるベンジャミン・リベットが1983年におこなった「自由意志の実験」では、人が運動するとき「動くぞ」と思う前から、脳が動く準備をはじめることがわかりました。
このことから、やる気は出そうと思って出すものではなく、行動の準備段階で無意識に出るものだと考えられます。そのため、意識的にやる気を出そうと思っても難しいのです。
ただし、脳は無意識の判断を下すとき、直前に受けた刺激やこれまでの記憶・経験の影響を受けるとされています。勉強したくないときは、やる気を出すことに時間をかけるよりも、小さな行動で脳に刺激を与えてやる気を引き出し、大きな行動へつなげていくのがおすすめです。
勉強したくないときでも勉強をする方法
勉強したくないときでも、以下の方法をとることで勉強を進められます。
● 最初にやること・ゴールを決めておく
● 勉強方法を柔軟に変える
● ご褒美を用意する
● 友達と一緒に勉強する
● 場所を変える
● 気分転換をする
● やりたいことを先にやる
● 必ず勉強しなければならない時間をつくる
ひとつずつ試して、自分に合った最適な方法を見つけましょう。
最初にやること・ゴールを決めておく
心理学者ビクター・ブルームが提唱した「期待理論」を応用し、最初にやることとゴール(目標)を決めて、やる気を高めたうえで勉強を進める方法があります。
期待理論では、「努力」「成果」「魅力度」の3つの要素が掛け合わされることで、やる気につながるとされています。少し頑張れば実現できる目標を決め、魅力的なご褒美を設定すると「よし、やるぞ!」と意欲がわきます。
設定の例は、次のとおりです。
| 項目 | 目標 | ご褒美 |
|---|---|---|
| 勉強のスタート | 問題集を開き、1問目を解く | チョコレートをひとかけら食べる |
| 勉強のゴール | 問題集を2ページ終わらせる | 1時間ゲームをする |
この方法は、目標を達成するとやる気が落ちてしまう特徴があるため、勉強の習慣を身につけたい人におすすめです。繰り返すなかで、目標を達成することに喜びを感じるようになり、ご褒美がなくても頑張れるようになるでしょう。
勉強方法を柔軟に変える
やる気が出ない背景に、勉強方法が自分に合っていない可能性が考えられるため、柔軟に勉強方法を変えてみましょう。
自分にとって楽しい、あるいはワクワクする方法が見つかれば、ドーパミンの放出にもつながり、やる気アップも期待できます。
教科書・ノートを使う以外の勉強方法の例は、次のとおりです。
● 参考書を読む
● 問題集を解く
● 勉強した内容の解説記事を作る
● スマートフォンアプリ・ゲームを使って問題を解く
● ゲームソフトを使って漢字や英単語を覚える
● 歴史の漫画を読む
● YouTubeを見て理解する
算数・数学のスマートフォンアプリで計算問題を解くのが好きな人は、勉強のスタートにそれをやり、やる気を上げてから問題集に挑戦すると効果的です。
ご褒美を用意する
勉強が終わったあと、ご褒美を用意しておくと、やる気がアップして頑張れる人もいるでしょう。例えば、チョコレートやアイスなどのおやつや、ゲーム・テレビなど楽しい行動をご褒美に設定します。
その都度ご褒美を設定するほかにも、ポイント制にして10ポイント貯まったら新しいゲームを買えるという方法もあり、楽しみながら勉強を頑張れます。
ただし、ご褒美に頼りすぎると、ご褒美がもらえないと頑張れなくなるため、ご家族と相談して適度にご褒美を設定することが大切です。
友達と一緒に勉強する
一人で頑張れないときは、友達と一緒に勉強する方法もあります。友達が勉強している姿を見ると「自分も頑張ろう!」と思って、やる気が上がることもあるでしょう。
問題を出し合ったり、わからない問題を教えてもらったり、協力して勉強を進められます。
ただし、友達とのおしゃべりが楽しくなって勉強が進まないようであれば、ほかの方法が合っているかもしれません。
場所を変える
家では、ゲームや漫画などの誘惑も多いため、楽しいほうへ流れてしまいがちです。家で勉強したくない気持ちが強くなるのであれば、場所を変えてみてはいかがでしょう。
図書館や学校、友達の家、地域のコミュニティセンターなど、人がいたり雑音があったりする環境のほうが集中できる人もいます。
気分転換をする
勉強をスタートしたものの、やっぱりやる気が出ないこともあるでしょう。その場合は、気分転換を挟んで、リフレッシュしてから再度取り組む方法もあります。
気分転換の例は、次のとおりです。
● 音楽をきく
● 仮眠をとる
● 運動をする
● おしゃべりをする
● 動画をみる
時間を決めて気分転換をし、長々と休憩してしまうのを防ぎましょう。
やりたいことを先にやる
思い切って勉強を後回しにしてしまう方法もあります。特に、やりたいことがあって勉強をしたくない人におすすめです。
ただし、やりたいことに割く時間は決めて、終わったら勉強に戻るなどルールを守るのが大切です。また、毎回勉強を後回しにするのではなく、ほかの方法も試してみてください。
必ず勉強しなければならない時間をつくる
勉強を習慣化したいのにもかかわらず、やる気が出なくて頑張れない人は、自分の意思とは関係なく勉強しなければならない環境を作るのがおすすめです。
例えば、毎週水曜日は家庭教師や塾を活用して、必ず勉強しなければならない環境にします。お金をかけたくない場合は、お家の人の力を借りて、ストップウォッチで時間を計ってもらったり、声をかけてもらったりしてもよいでしょう。
勉強をしたくなるためには?勉強したくない理由を解決しよう
勉強したくない人のなかには、勉強したいと思う人になりたいと考える人もいるようです。たしかに「勉強したい!」と、やる気に満ちあふれていたら、楽しく勉強を続けられますよね。
ここでは、勉強をしたくなるために、勉強したくない理由と解決方法を解説します。
● 勉強する意味がわからない
● 勉強よりやりたいことがある
● 勉強してもわからない
● 勉強がおもしろくない
● 勉強しすぎて疲れた
自分にあてはまる理由があれば、解決方法を試してみてください。
勉強する意味がわからない
勉強すると、新たな知識や考え方が身につき、深く物事を考えたり問題を解決したりと、できることが増えます。
最近は、インターネットで新しい知識や情報をすぐに得られますが、間違った情報も含まれています。勉強を重ねると、間違った情報に気づく力が身につき、自分の身を守ったりより豊かな生活を送ったりできるのです。
このように、勉強とは単に知識を覚えるのではなく、正しく考える力を身につけ、日常に活かすために重要です。
それでも勉強する意味を見い出せない人は、勉強するメリットをおさらいしてみましょう。
勉強するメリットは、次のとおりです。
● 進路の幅が広がる
● 努力の意味を実感できる
● 達成感を味わえる
勉強は、意味よりも目的をはっきりさせることが大切です。「〇〇大学に行きたい」「将来、プログラマーになりたい」など、将来の夢を叶えることを目的にするとやる気につながります。
将来の夢がない人も、いざやりたいことが出てきたとき、基礎学力があれば自由に進路の選択が可能です。
また、勉強を通じて目標を達成すると、努力する意味や達成感を味わえます。勉強で身に着いた努力の仕方は、スポーツや習い事でも活かせるでしょう。
勉強よりやりたいことがある
勉強よりもやりたいことがある人は、やりたいことを優先してもよいでしょう。
ただし、高校・大学受験を考えているのであれば、勉強する時間も必要です。すき間時間をうまく活用し、やりたいことにしっかり時間を割けば、両立できるでしょう。
すき間時間を活用した勉強方法は、次のとおりです。
● 移動中にスマートフォンアプリ・ゲームを活用する
● 空いた時間で家庭教師・塾を活用する
● オンライン家庭教師を活用する
● 学校に行く前の時間を勉強に充てる
学生時代にスポーツや芸術に打ち込むことで、習得できる技術や感性もあります。勉強だけではなくやりたいことにもしっかり打ち込み、充実した生活を送ってください。
勉強してもわからない
勉強してもわからないことが多い人にとっては、勉強時間が苦痛になり、やりたくない気持ちになります。
その場合は、わかること・できることからはじめてみてください。
例えば、数学の方程式がわからないときは、その前の単元のできる問題から手をつけてみましょう。少しずつ難易度を上げ、わからなかったらわかるところまで戻って、少しずつ進めます。
どうしても解決できない場合は、学校の先生に聞いてわからないところを解消していきましょう。自分一人で頑張るのではなく、できる人や得意な人に頼ることが大切です。
勉強がおもしろくない
勉強がおもしろくないと感じる人もいるでしょう。
なにもかもをおもしろいと思って過ごせる人は少ないため、勉強がおもしろくなくても不思議ではありません。ただし、おもしろくないけれどやらなければならないことに対し、どのように向き合うか、また進めていくかを考える必要があります。
向き合う方法として、目的の明確化やご褒美の設定などが考えられます。また、勉強する習慣を身につければ、気持ちとは関係なく淡々と勉強を進めることも可能です。
「おもしろくないからやらない」と決めるのではなく、「おもしろくはないけれど自分のためにやる」と考えられれば、進路選択の幅が広がるでしょう。
勉強しすぎて疲れた
勉強したくない人のなかには、勉強のしすぎで疲れてしまった人もいるでしょう。その場合は、思い切って休むことも大切です。
しばらく休むと、またやる気がわいてくることもあるはずです。休むのが心配な人は、簡単な勉強だけやっておき、難易度が高いものは元気なときにやるなど、メリハリをつけて進めてみましょう。
自分のペースで勉強を進めたい人へ
勉強したくない人のなかには「自分のペースでゆっくりやりたい」「わからないところを解決してから次に進みたい」と考えている人もいるのではないでしょうか。
学校の授業進度が自分に合っていないと、わからないことが増えてしまいます。その結果、勉強がおもしろくなくなったり、意味を見い出せなくなったりして、勉強したい気持ちが薄れるでしょう。
自分のペースで勉強を進めたい人は、通信制高校を検討してみるのがおすすめです。
通信制高校は、オンライン授業や自宅学習で学習を進められる高校です。毎日学校に通う必要がなく、また在学しなければならない期間が3年以上となっていることも多いため、自分のペースでゆっくり学びたい人に合っています。
通信制高校である明聖高校は、全日制と同じように3年間で卒業資格を取得できるようカリキュラムが組まれていますが、単位を修得できなくても次年度に再履修が可能です。自宅でのオンライン学習が中心であるため、周りの目を気にせず勉強と向き合えます。
WEBコース|明聖高等学校
まとめ
勉強したくないときは、やる気を出す方法を探しがちですが、やる気を出すよりもその状態で勉強する方法を身につけるほうが効率的です。本記事で紹介した方法を試しながら、自分に合った勉強方法を見つけてみてください。もし、勉強がわからなくてやりたくない気持ちが強いのであれば、自分のペースで勉強を進められる通信制高校への進学も考えてみましょう。わかるまでじっくりと勉強に向き合えるため、わかる楽しさを味わいながら自分のペースで学べます。
参考URL:
第23回 脳の中の「快楽」センター|日本脳科学関連学会連合
「ご褒美がもらえる」と「大変だけど頑張ろう」の2つの『やる気』システムを解明 〜うつ病の仕組みとその改善法を知る上で重要な手がかり〜|国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構
通信制高校とは?全日制・定時制との違い、それぞれの特徴を解説|通信高校生ブログ|明聖高等学校
モチベーション脳「やる気」が起きるメカニズム (大黒 達也 著)|NHK出版新書

明聖高等学校は、千葉・中野にキャンパスを構える通信制高校です。全日コース・全日ITコース・通信コース・WEBコースに分かれており、一人ひとりに合わせた高校生活を過ごすことができます。